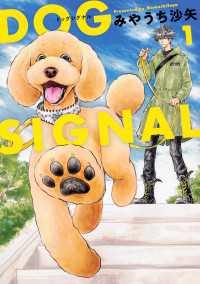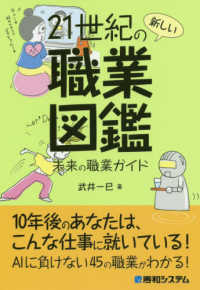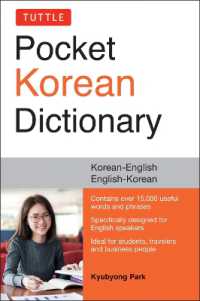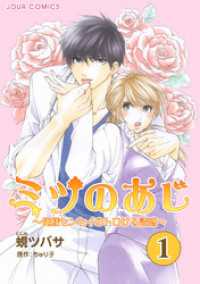内容説明
知識偏重型教育から概念形成型教育へ。「イイクニつくろう鎌倉幕府」とかつては覚えたものですが、今は、「イイハコつくろう鎌倉幕府」と覚えるらしいのです。それで、中身は変わるのでしょうか。地動説を学校で習ったのに、「太陽は東から上って西に沈む」と考えているのでは天動説のままです。言葉を知っているのは、知識の入り口の話です。同じ教科書で同じ授業を受けたのに、なぜ人間の能力は多様になってしまうのでしょうか。それは、考えるプロセスが違い、理解の質も違い、そのために成果も違うからです。それならば言葉・ことばを使って考えが深まった場合、成果もまた同じ言葉・ことばのままなのでしょうか。本書では、今話題の「概念型カリキュラム」を例にして、言葉の意味と概念との違いを検討してみます。
目次
第1章 サブジェクト・マター(教科内容)
第2章 一次元カリキュラムの教科課程
第3章 二次元カリキュラムの教科課程
第4章 三次元カリキュラムの教科課程
第5章 概念形成を支援する授業作り
第6章 大学の授業
第7章 概念型カリキュラムの教育優位性
第8章 個人的経験と理論が出会う時
第9章 内言2―形をなくした意味の世界
著者等紹介
福田誠治[フクタセイジ]
1950年岐阜県生まれ。1979年より42年間都留文科大学に勤務。元都留文科大学学長、前都留文科大学理事長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。