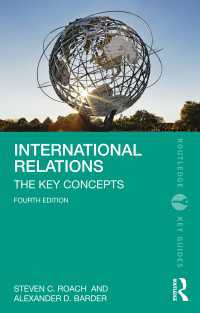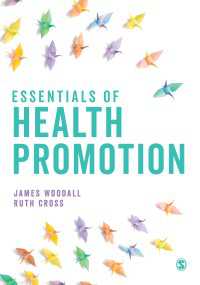目次
第1章 黎明期・希少価値の高い馳走(乾しいたけの歴史―9~13世紀;室町~江戸時代の乾しいたけ食文化・流通―15~19世紀中頃)
第2章 隆盛期・そして待ち受ける試練(乾しいたけ産業の夜明け―明治~太平洋戦争末期頃(1868~1944年)
乾しいたけ産業の勃興―昭和20~40年代中頃
輝ける黄金時代―昭和46~60(1971~1985)年頃
厳しい冬の時代―昭和61年~平成18(1986~2006)年頃
ふたたび転記が訪れる―平成19(2007年)~)
第3章 復活への課題と未来につなぐ灯(明日への道;生産・流通の課題;千年も続く輸出の灯を消してはならない;乾しいたけ―千年の歴史をひもとく 年表;乾しいたけ関連資料)
著者等紹介
小川武廣[オガワタケヒロ]
日本椎茸農業協同組合連合会顧問。きのこアドバイザー。日本産・原木乾しいたけをすすめる会顧問。昭和3年、奈良県生まれ。京都大学農学部林学科卒業。昭和28~53年、林野庁(うち5年半、農林水産航空協会、群馬県に出向)、昭和53~平成23年、日本椎茸農業協同組合連合会、同連合会会長などを経て、現在に至る。日本きのこ研究所理事、森喜作記念椎茸振興基金運営委員なども歴任(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
さっちも
12
9世紀ごろから「乾燥しいたけ」を日本は栽培していた。中国からの模倣ではじめた産業だが、最初の頃から中国への輸出が主で国内消費は少なかったというのが面白い。養殖が盛んになる、江戸ごろにようやく輸出と国内消費が拮抗するという。昭和のはじめまで続いたのだから、中国の乾燥しいたけ依存は1000年に及んだことになる。昭和の40年までは「松茸」より高値だった高級食材。今はすっかり忘れさってしまっているのは何事だろうかと思う。もちろん自分も含めてだが、足下にある豊かさを知らずに新規の何かばかりにやっきになる2023/04/27
紅独歩
2
「しいたけ」の本ではない。「乾しいたけ」の本。すなわち生物学ではなく、社会学・経済学的内容。といっても読みにくいものではない。千年の歴史から浮き彫りにされるのは、高級輸出資源としての乾しいたけであり、中国との関係の深さだ。中国の人工栽培成功によって、輸出→輸入に逆転し国産乾しいたけは苦境にたっているという。森喜作によって安定した人工栽培法が確立されてわずか70年あまり、千年の歴史を閉じるのはあまりにも惜しい話だ。お歳暮・お中元には国産乾しいたけを!2012/10/01