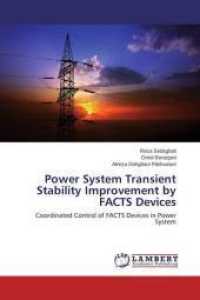- ホーム
- > 和書
- > 社会
- > 社会問題
- > マスコミ・メディア問題
出版社内容情報
地震や洪水などの大きな災害時に、被害を軽減するために設置されるラジオ局である臨時災害放送局。東日本大震災で注目され、2016年の熊本地震や17年の九州北部豪雨でも設置された。
コミュニティFMとの違いなど基本的なポイントを紹介したうえで、東日本大震災後に作られた宮城県や福島県の臨時災害放送局をフィールドワークして、行政情報や生活情報などをどう発信したのか、実態調査の成果を明らかにする。
国主導で進められる復旧・復興に対して、被災地の人々を結び付け、要望をすくい上げる臨時災害放送局の役割を浮き彫りにして、災害復興と放送・メディアの今後のあり方を指し示す。
序 章 東日本大震災での臨時災害放送局の取り組み
第1章 コミュニティFMと臨災局
1 コミュニティFM
2 臨災局
3 コミュニティFMと臨災局の比較
4 臨災局長期化の実情
5 被災地に存在する創発的コミュニティ
6 なぜ臨災局の放送は長期化したのか
7 東日本大震災後の臨災局の調査
コラム1 認知されていなかった臨災局
第2章 やまもとさいがいエフエム「りんごラジオ」
1 山元町の概要
2 りんごラジオ開局までの経緯
3 りんごラジオの日常
4 りんごラジオの放送内容を分析する
5 りんごラジオと報道特別番組
6 スペース・メディアとしてのりんごラジオ
コラム2 放送運営は過去の反省を投影したもの
第3章 みなみそうまさいがいエフエム「南相馬ひばりFM」
1 南相馬市の概要
2 ひばりエフエム開局までの経緯
3 ひばりエフエムの日常
4 臨災局としてのひばりエフエム
コラム3 生放送中に市民から「助けてください」とSOSメール
第4章 とみおかさいがいエフエム「おだがいさまFM」
1 富岡町の概要
2 おだがいさまFM開局までの経緯
3 おだがいさまFMの日常
4 臨災局としてのおだがいさまFM
コラム4 災害時の方言対策
第5章 臨災局の長期化の実態
1 長期化する臨災局の段階分け
2 臨災局とコミュニティの関係
3 臨災局のなかの双方向性(対面性)
4 放送制度としての問題点
参考文献
あとがき
大内 斎之[オオウチ ナリユキ]
著・文・その他
内容説明
地震や豪雨などの大きな災害時に、被害を軽減するために設置されるラジオ局である臨時災害放送局。コミュニティFMとの違いなどを押さえたうえで、東日本大震災後に作られた各局をフィールドワークして、その知られざる役割やメディアとしての今後の可能性を明らかにする。
目次
序章 東日本大震災での臨時災害放送局の取り組み
第1章 コミュニティFMと臨災局
第2章 やまもとさいがいエフエム「りんごラジオ」
第3章 みなみそうまさいがいエフエム「南相馬ひばりFM」
第4章 とみおかさいがいエフエム「おだがいさまFM」
第5章 臨災局の長期化の実態
著者等紹介
大内斎之[オオウチナリユキ]
1958年、東京都生まれ。新潟大学大学院現代社会文化研究科博士研究員兼非常勤講師。専攻は地域メディア、メディア災害報道(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。