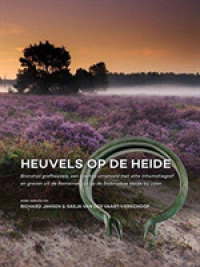出版社内容情報
第1 章 食品業界の現状および 食品特許の特性
1.1 食品は一過性のブームになりやすく,マネされやすい
1.2 食品は特許で活きる
1.3 食品特許のメリット・デメリット
第2 章 食品特許と営業利益との関係
2.1 特許庁が実施する知的財産活動調査
2.2 食品特許は営業利益高に大きく影響する
2.3 特許の食品に対する親和性
2.4 特許が企業価値に与える影響
2.5 日本の市場と海外の市場
2.6 利益につながる外国特許のインパクト
2.7 競合他社は外国出願している
第3 章 食品特許の手がかり
3.1 価値ある特許とは
3.2 課題なくして発明なし
3.3 侵害対策・特許審査対策としての課題の具体化
3.4 発明のつくり方の原理
3.5 発明のつくり方の手順
3.5.1 第1 段階:資料集め
3.5.2 第2 段階:資料の咀嚼
3.5.3 第3 段階:データからの解放
3.5.4 第4 段階:アイデアの誕生
3.5.5 第5 段階:アイデアのチェック
3.6 組織的な発明の創出
3.6.1 知的財産経営のジレンマ
3.6.2 事業目的とリンクした発明発掘
3.6.3 会社の「あるべき姿」の明確化(Phase I)
3.6.4 会社の「現在の姿」の明確化(Phase II)
3.7 知的財産担当者のあるべき姿
3.7.1 知的財産担当者に欠かせない素養:「積極的な行動」
3.7.2 発明を正確に把握するための3 つのスキル
3.7.3 情報を引き出すスキル
3.7.4 長文作成力は必要か?
3.7.5 経験に基づく知識の吸収
3.7.6 知的財産権の知識
3.7.7 知的財産担当者のバリエーション
第4 章 食品特許を取得する方法
4.1 食品特許を取得するための基礎知識
4.1.1 特許出願に必要なもの
4.1.2 願書(特許願)
4.1.3 特許請求の範囲
4.1.4 明細書
4.1.5 図 面
4.1.6 要約書
4.1.7 その他の書面
4.1.8 明細書と研究報告書との比較
4.2 発明の裏付け
4.2.1 発明を裏付ける記載
4.2.2 実施可能要件
4.2.3 実施可能要件を充足する実施例
4.2.4 実施例の作成主体・記載内容
4.2.5 実施例の充実の程度
4.2.6 効果的な実施例
4.2.7 比較例は慎重に
4.2.8 実施例の記載の留意点
4.3 発明の特許要件
4.3.1 6 つの特許要件
4.3.2 特許要件の概要
4.4 新 規 性
4.4.1 新規性の概要
4.4.2 公然知られた発明
4.4.3 公然実施をされた発明
4.4.4 頒布された刊行物
4.4.5 刊行物に記載された発明
4.4.6 電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明
4.4.7 引用発明の適格性
4.4.8 上位概念と下位概念
4.5 進 歩 性
4.5.1 進歩性の概要
4.5.2 当業者
4.5.3 本願発明および引用発明の認定
4.5.4 引用発明の選択
4.5.5 進歩性が否定される方向に働く要素
4.5.6 本願発明の有利な効果
4.5.7 阻害要因
4.5.8 進歩性の判断における留意事項
4.6 パテントマップのつくり方・使い方
4.6.1 パテントマップとは
4.6.2 パテントマップをつくる前に
4.6.3 パテントマップのつくり方
4.6.4 パテントマップの作成例
4.6.5 パテントマップの使い方
第5 章 食品特許の利活用のためのTips
5.1 食品発明の種類
5.2 プロダクト・バイ・プロセスクレーム
5.2.1 プロダクト・バイ・プロセスクレームとは
5.2.2 PBP クレームと非PBP との境界
5.2.3 不可能・非実際的事情
5.2.4 最高裁判決の実務への影響
5.3 機能性食品と食品の用途特許
5.4 製法特許の有効性
5.5 官能評価に基づく実施例
5.5.1 事例1
5.5.2 事例2
5.5.3 事例3
5.5.4 事例4
5.5.5 事例5
第6 章 食品特許の具体的な活用事例・係争
6.1 食品特許の活用事例
6.1.1 食品特許に基づく市場参入
6.1.2 中小企業の食品特許活用事例
6.2 食品特許の代表裁判例(1):切餅事件
6.2.1 特許権の効力および特許請求の範囲の解釈
6.2.2 切餅事件における裁判所の判断
6.2.3 第一審による構成要件B の解釈
6.2.4 第二審による構成要件B の解釈
6.2.5 第一審および第二審における出願経過の参酌
6.2.6 第一審と第二審の相違点
6.2.7 証拠能力
6.2.8 損害額の認定
6.2.9 時機に後れた攻撃防御方法
6.2.10 特許実務へのフィードバック
6.3 食品特許の代表裁判例(2):ドリップバッグ事件
6.3.1 事件の概要
6.3.2 原告特許発明および被告製品の概要
6.3.3 原告特許発明と被告製品との相違点
6.3.4 原告および被告の主張
6.3.5 第一審裁判所の判断
6.3.6 第二審裁判所の判断
6.3.7 特許実務へのフィードバック
巻末付録1 用語・説明
巻末付録2 特許出願から特許登録までの流れ
森本敏明[モリモトトシアキ]
著・文・その他
目次
第1章 食品業界の現状および食品特許の特性
第2章 食品特許と営業利益との関係
第3章 食品特許の手がかり
第4章 食品特許を取得する方法
第5章 食品特許の利活用のためのTips
第6章 食品特許の具体的な活用事例・係争
著者等紹介
森本敏明[モリモトトシアキ]
1975年生まれ。2000年東京理科大学大学院基礎工学研究科修了。同年、山之内製薬株式会社(現アステラス製薬株式会社)に入社。バイオ医薬の工業化研究、製剤の化学分析などに従事する。2006年弁理士登録。同年特許事務所に入所。2010年モリモト特許商標事務所を開業。2012年株式会社モリモト・アンド・アソシエーツを設立。主に食品、医薬・医療、化粧品、材料、環境などの化学・バイオ発明の特許権利化、特許調査、係争業務に従事する(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
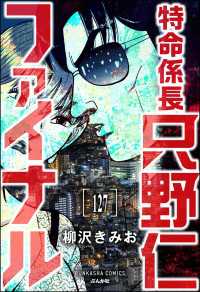
- 電子書籍
- 特命係長 只野仁ファイナル(分冊版) …