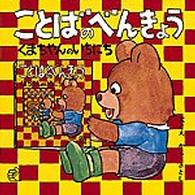内容説明
人と人とのつながりが弱くなったり・壊されたりすることの多い現今、こうしたつながりを回復するにはどうしたらよいのだろうか。共感と道徳性の発達研究の世界的権威であるホフマンが、この点をめぐっての30年にわたる研究と思索の結果をまとめたライフワーク。共感とは、「自分の置かれた状況よりも他人の置かれた状況にふさわしい感情」であるが、この感情が人と人とのつながりを生み出す。ホフマンはこのことを、5つの道徳的出会いの場面と5つの共感喚起の様式について発達的に検討する。
目次
1部 罪のない傍観者
2部 違背
3部 仮想の違背
4部 共感だけで十分か
5部 共感と道徳的原理
6部 文化
7部 介入
著者等紹介
ホフマン,マーチン・L.[ホフマン,マーチンL.][Hoffman,Martin L.]
ニューヨーク大学教授
菊池章夫[キクチアキオ]
岩手県立大学社会福祉学部福祉経営学科教授。教育学博士
二宮克美[ニノミヤカツミ]
愛知学院大学情報社会政策学部教授。教育学博士
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ほろ
1
発達分野での共感の扱われ方。自他境界については,発達の文脈と臨床の文脈は異なることはこれで明らかになった。過剰さの定義については再考したいところ2020/02/28
抹茶ケーキ
0
共感とは何か、個人の中でどのように発達するか、それはロールズなどの普遍的命法とどのように関わるか。タイトルは発達だけど、発達についての箇所よりも、後半の倫理学っぽい内容が面白かった。ロールズの命法は共感を基本的に排除しているけれども、実際のところそれは誤りで、「無知のベール」下での判断にも共感は必要とされるので、共感はそれ自体では倫理命法たりないけれども、それを支える重要な要素であるとのこと。共感のいいところだけではなく、悪いところにも紙幅を割いた上で、共感は必要だと言っているので、説得力があると感じた。2017/02/04