内容説明
「おたがいさま」の暮らしのビジョンをつくりあげる「現代版社会事業家」になるために、私たちは何をどう考え、何に取り組めばいいのか。「制度に振り回される」次元ではなく、「制度を使いこなす」次元の人になるために。
目次
第1部 伴走型支援とは何か―その社会的背景・思想・仕組み(生活困窮をめぐる新たな状況―なぜ伴走型支援が必要なのか;伴走の思想と伴走型支援の理念・仕組み)
第2部 伴走型支援の成果と課題(伴走型支援としてのパーソナルサポート事業の展開―福岡絆プロジェクト;若年生活困窮者への伴走型就労・社会参加支援―北九州におけるモデル事業)
第3部 これからの生活困窮者支援のあり方(相互多重型支援―これからの生活困窮者支援の構想と展望;座談会:これからの生活困窮者支援はいかにあるべきか)
著者等紹介
奥田知志[オクダトモシ]
認定NPO法人北九州ホームレス支援機構理事長、日本バプテスト連盟東八幡キリスト教会牧師、公益財団法人共生地域創造財団代表理事、北九州市立大学MBA特任教授
稲月正[イナズキタダシ]
北九州市立大学基盤教育センター教授
垣田裕介[カキタユウスケ]
大分大学大学院福祉社会科学研究科准教授
堤圭史郎[ツツミケイシロウ]
福岡県立大学人間社会学部講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ゆう。
22
本著は、生活困窮者に対する伴走型支援とは何か、また生活困窮者自立支援法をどのように活用していくことが大切なのかを考察した本です。伴走型支援については、その考え方だけではなく実践も紹介されています。伴走型支援は問題解決型ではなく「伴走そのものに意味がある」という考え方に立ちます。従来の支援する・される関係を超えた、共同的関係性を「伴走型」として捉えているのではないかと僕は考えました。そういう意味では学び多い理念です。ただ、本著では生活困窮者自立支援法に対する評価は肯定的です。そこが少し疑問もわきました。2015/06/14
1.3manen
19
現在の生活困窮問題の根底にあるのは、経済的困窮と社会的孤立の複合(13頁)。NEET、ひきこもり、SNEPいずれもそうだと思う。公的支援などあてにならない。ハロワに行っても役に立たないので。社会的排除は、分配と関係に関する概念(18頁)。非正規は本人の責任でなく、国際的な経済状況、国家の労働政策、人口構造に起因(同頁)。同感。玄田有史(2013)を1次資料とするスネップ20~59歳の棒グラフの増え方を厚労省はどう思うのか? 2014/08/24
ねこっく
5
論理立てて伴走型支援が説明されている名著。 まず1では、日本の困窮者の現状を厚生労働省のデータを使いながら展開。ホームレスとハウスレスの違いなど、基本的な概念を押さえながら理解できる。 2では、この本が取り組んでもいる困窮者支援プロジェクトの奏功を個別の検証データを元に見ることができる。興味深いのが、やはり人間とは誰か心配してくれる人がいれば、回復していく傾向があることだ。 最後に専門家たちによるトークが交えられる。複合的な視点で困窮者支援の在り方を模索している。 自尊感情と自己有用感のバランス、が大切。2022/04/04
-
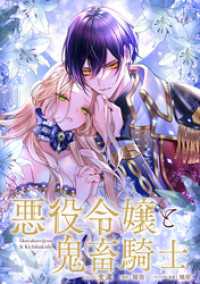
- 電子書籍
- 悪役令嬢と鬼畜騎士 連載版: 24 Z…
-
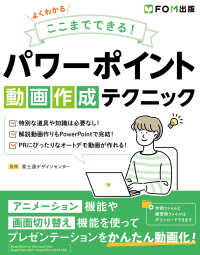
- 電子書籍
- よくわかる ここまでできる! パワーポ…
-
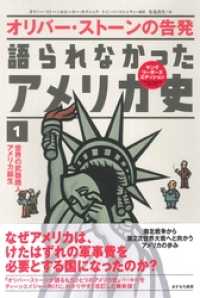
- 電子書籍
- 語られなかったアメリカ史①世界の武器商…
-
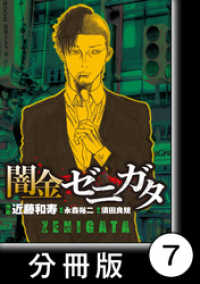
- 電子書籍
- 闇金ゼニガタ【分冊版】(7) バンブー…
-
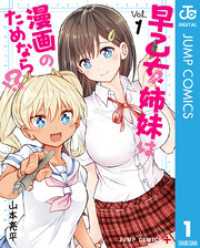
- 電子書籍
- 早乙女姉妹は漫画のためなら!? 1 ジ…




