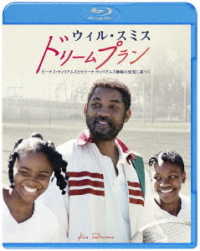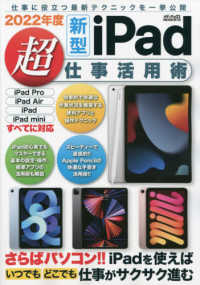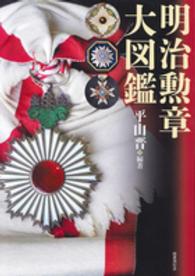内容説明
慶長12(1607)年、朝鮮王朝から江戸時代最初の外交使節が未訪する。幕府は海路~陸路を経て江戸をめざす使節の接待を命じ、道中諸藩の御馳走人がそれに応えた。一行をもてなした饗応料理の食材はいかに調達・調理されたのか?200年にわたる朝鮮通信使饗応の記録をたどり、日朝両国の“食文化の交流”をひもとく。
目次
1 慶長度から文化度にかけての饗応
2 饗応料理の内容(道中の七五三と五五三;国書伝命時の七五三 ほか)
3 好物の食料(朝鮮人の好物;鳥獣肉類 ほか)
4 日本の食文化に与えた影響(食料調達方法の確立;朝鮮料理の影響を受けた料理や菓子 ほか)
5 朝鮮の食文化に与えた影響(さつまいも;とうがらし)
著者等紹介
高正晴子[タカマサハルコ]
1943年大阪市生まれ。1966年同志社女子大学学芸学部家政学科卒業。2008年梅花女子大学短期大学部退職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Toska
20
江戸時代に日本を訪れた朝鮮通信使がどのような饗応を受けていたか、というマニアックだが奥の深い研究。通信使の訪問は将軍の治世を寿ぐ大イベントで、接待のため幕府の歳入を上回る(!)予算がかかったとのこと。これは双方にとって負担が大きく、江戸後期には規模の縮小が図られたようだ。また、最高ランクの「七五三」膳は格式が高すぎて儀礼食と化し、最後は模型で代用するようになったという(勿論、食べられる料理も出している)。外交の本質を物語るようなエピソード。2025/07/20
なかのっこ
1
今ではなじみのない食材も出てきてあまりぴんとこないところもあったけど、とりあえず、朝鮮通信使が毎日お腹いっぱい食べてたことは理解した。絶対太ったと思う。2015/05/27
光太郎
0
彼らの饗応されたメニューが詳しく残っていたのである2014/08/31