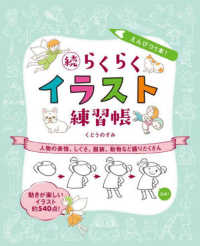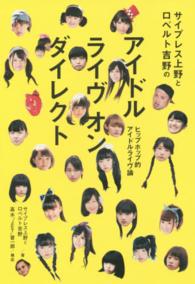出版社内容情報
社会福祉基礎構造改革、まちづくり、交通バリアフリー、介護保険、ジェンダー問題、ソーシャルワーカーの専門職性など、多岐にわたるテーマを、著者の実践・研究をふまえて社会福祉実践の観点から見通す。
はじめに
1章 福祉システム改革事情
1 高齢率日本一の風景
2 福祉とフクシ
3 福祉システムのパラダイム転換
4 社会福祉基礎構造改革の概要
(1) 要点/(2) 目的および基本理念の変化/(3) 措置制度から利用制度への変更/(4) 利用者の保護と福祉サービスの質の確保/(5) 地域福祉の推進
5 社会福祉基礎構造改革のキーワード
(1) 福祉サービス/(2) 個人の尊厳・自己決定権・自立支援
6 社会福祉基礎構造改革の課題
(1) 改革が積み残したもの/(2) 地域福祉計画と“協生”システムの模索
2章 福祉のまちづくり
1 福祉のまちづくりと地域福祉計画
(1) 福祉のまちづくりの意味/(2) 福祉のまちづくりの現状~調査と実態の乖離
2 バリアフリーのまちづくり
(1) 一般化/(2) 施策化
3 ADAの国
(1) 旅立ち/(2) ライト州立大学のイージーライダーたち/(3) 私たちの教育姿勢を問い直させる学生会館/(4) ディスアビリティ・サービスに携わるのは二〇〇人/(5) 障害を理由に採用拒否はできない/(6) 法は運保険と地域ケアシステム
1 介護保険施行から三年を経過して
2 介護調査報告
(1) 実態調査の概要/(2) 介護保険による変化
3 介護調査から見えてきたもの
(1) 自立認識の乖離/(2) 要介護認定/(3) 家事援助サービス/(4) 介護予防の経済学/(5) 家事援助サービス軽視の背景
4 介護問題の課題と展望
(1) 要介護認定と家事援助サービス/(2) 地域ケアの新たなシステムを~東和町の事例から~
5章 老いのセクシャリティ
1 『君の名は』
2 高齢期の老いと性
3 性とエイジズム
(1) エイジズムと老年学/(2) 高齢者の性研究の現在/(3) 老人介護の現場
4 セクシャリティの視点
(1) セックス・ジェンダー・セクシャリティ/(2) 老いとセクシャリティ/(3) セクシャリティ研究の現在/(4) 老いとセクシャリティの男女差
5 共生思想を超えて
6章 ソーシャルワーカーのアイデンティティ
1 アイデンティティ形成の必要性
(1) イメージの不在/(2) 学生のイメージ/(3) 実習というアイデンティティ形成の場
大学教師となって五年。年齢だけはベテランの域に達しているというのに、研究者としても教育者としてもまだまだ駆け出しだ。だからこそ、毎日が新鮮でもある。教育については、少しばかり手応えのようなものが感じられるようになった。一人ひとりの学生に対して、さまざまな角度から模索しながら診断的評価や形成的評価をするおもしろさに遭遇したからだ。学生たちの反応や成長の度合いに、一喜一憂する、そんな教育活動の合間に自分なりに必死に書き綴って発表したいくつかの拙稿に大幅加筆し、ひとつにまとめてみた。
私の社会福祉の教育研究職に携わった期間は短いものではあるけれど、この間の社会福祉は介護保険の導入、社会福祉基礎構造改革と、いままで以上に激動の時代を経験したのではないだろうか。はじめて教職についた一九九九年は、介護保険実施一年前であった。「高齢社会をよくする女性の会」や「一万人市民委員会」で、いわば中央の方から介護保険にかかわってきた私にとって、宮崎県という地域で職場の同僚に恵まれて実態調査が実現したのは、実に幸運であった。調査は介護保険導入前後の三年間にわたって実施した。この二、三年というもの介護保険におけるさまざまな問題は出域ケアという、いわば間接援助と直接対人援助が重複する部分として押さえ展開した。5章は直接援助を支える理念の検証のために、性問題を取り上げセクシャリティとジェンダーの視点で照射した。6章は、学生がソーシャルワーカーとして社会に巣立っていくためには、教育の場でソーシャルワーカーとしてのアイデンティティを形成することが必要だと考え、その方法の解明を試みた。解明のプロセスで半ば偶然にアイデンティティ形成のメカニズムを発見したのだった。このメカニズムによって、今後の教育方法の方向性が少なからず獲得できたような気がする。
本書は章ごとに独立しているので、どの章からでも入りやすいところから読んでいただければと思う。あえて起承転結の作法に重ね合わせるならば、起の部分が1章、承の部分が2、3、4、5章で、6章が転でありつつ結への方向性ということになるだろうか。したがって結を探求する作業が今後もたっぷりと残されているということだ。なお弁解がましいが、私自身、1章についてはこなれが悪くて思いが十分伝わらないのではないかとの危惧をもっており、最後にお読みいただくほうがよいかもしれない。
本書の表題にもなっている「協生」という
内容説明
本書のテーマは、社会福祉基礎構造改革、まちづくり、交通バリアフリー、介護保険、性問題、ソーシャルワーカーの専門職性と多岐にわたっている。1章は、今日のもっとも重要課題である社会福祉基礎構造改革を点検しながら、福祉システムの解明にアプローチしている。次に福祉のまちづくり、交通バリアフリーをテーマにして、2章、3章で間接援助技術における基本姿勢を探求している。4章は介護保険と地域ケアという、いわば間接援助と直接対人援助が重複する部分として押さえ展開した。5章は直接援助を支える理念の検証のために、性問題を取り上げセクシャリティとジェンダーの視点で照射した。6章は、学生がソーシャルワーカーとして社会に巣立っていくためには、教育の場でソーシャルワーカーとしてのアイデンティティを形成することが必要だと考え、その方法の解明を試みた。
目次
1章 福祉システム改革事情
2章 福祉のまちづくり
3章 外出と交通のバリアフリー
4章 介護保険と地域ケアシステム
5章 老いのセクシャリティ
6章 ソーシャルワーカーのアイデンティティ
著者等紹介
井上由美子[イノウエユミコ]
1946年長崎市生まれ。1968年日本社会事業大学社会福祉学部卒業。1972年法政大学大学院社会科学研究科社会学専攻修士課程修了。1989年生活文化研究所所長。1999年九州保健福祉大学社会福祉学部社会福祉計画学科専任講師。2003年宇部フロンティア大学人間社会学部人間社会学科助教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
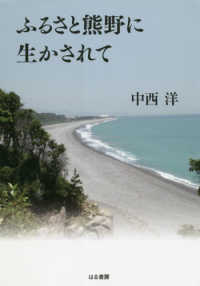
- 和書
- ふるさと熊野に生かされて