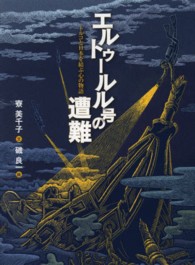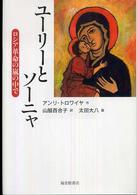出版社内容情報
「開発」という行為が人間にとっていかなる意味を持つのかを根源的に問う試み「開発」とは野蛮を文明に移行させる手段なのだろうか。また世界のよりよい方向性を定める行為なのだろうか。本書は、開発の技術を俯瞰し、方向性が大きく変化する歴史の転換点を思想史的に見つめ、日本から「国際開発」を世界へと発信する意味を模索する。そのうえで、歴史的見地から開発が人間にとって持つ意味を学問として位置付ける壮大な試みである。
はしがき
序 章 野蛮/文明から生存へ
第?部 開発・援助の知的技術
第1章 生活の質をどう評価するか
1 暮らしぶりの良さを比べる
2 生活水準観のうつりかわり
3 アマルティア・センの新しさ
4 ケイパビリティ・アプローチの批判的検討
5 操作化への課題
第2章 貧しい人々は何をもっているのか
1 「貧困」への問い
2 眼差しの系譜
3 貧困化のメカニズム
4 無いものから、在るものへ
5 開発研究はどこを見るべきか
第3章 たった一つの村を調べて何になるのか
1 ある論文コンテストで
2 開発の現場と「事例」
3 一般化とは何ぞや
4 比較と類型
5 少数事例の奥深さ
第?部 開発・援助の想定外
第4章 分業は何を生み出すのか
1 開発と分業
2 分業とリスク
3 分業と速度
4 分業と支配
第5章 「想定外」はなぜ繰り返されるのか
1 「想定外」への着目
2 「想定外」のメカニズム
3 開発される側の意外な反応
4 開発を仕掛ける側の学習条件
5 開発計画における学びと慎ましさ
第6章 緊急物資はなぜ届かないのか
1 届かない援助
2 財から人を眺める
3 エルスターの「ローカルな正義」
4 エルスター理論の拡張と財アプローチの限界
5 タイの事例が問いかけるもの
第7章 豊かな資源は呪いか
1 豊かな資源と貧しい人々
2 貧困と資源
3 「資源の呪い」
4 コモンズと政府の戦略
5 転換力と「呪い」の回避
第?部 開発・援助と日本の生い立ち
第8章 戦後日本は、なぜ援助に乗り出したのか
1 経済協力と国内事情
2 中進国日本の経済協力
3 賠償に先立つ経済協力
4 援助と国内事情の切り離し
5 援助理念探しの歴史的背景
第9章 日本に援助庁がないのはなぜか
1 集中か、分散か
2 分散型システムへの批判
3 援助行政一元化論
4 民間主導の文脈
5 分散型システムの利点
6 今、援助庁は必要か?
第10章 「日本モデル」はなぜ打ち出されなかったのか
1 開発と模倣
2 1950年代の日本の開発実践者の思考
3 特殊性の重視
4 「モデルを出さない」というモデル
終 章 開発の未来学??アイディアに力を
あとがき
人名・事項索引
佐藤 仁[サトウ ジン]
2016年6月現在東京大学東洋文化研究所教授・プリンストン大学ウッドロー・ウィルソンスクール客員教授
内容説明
「開発」とは野蛮を文明に移行させる手段なのだろうか。また世界のよりよい方向性を定める行為なのだろうか。本書は、開発の技術を俯瞰し、方向性が大きく変化する歴史の転換点を思想史的に見つめ、日本から「国際開発」を世界へと発信する意味を模索する。そのうえで、歴史的見地から開発が人間にとって持つ意味を学問として位置付ける壮大な試みである。
目次
第1部 開発・援助の知的技術(生活の質をどう評価するか;貧しい人々は何をもっているのか;たった1つの村を調べて何になるのか)
第2部 開発・援助の想定外(分業は何を生み出すのか;「想定外」はなぜ繰り返されるのか;緊急物資はなぜ届かないのか;豊かな資源は呪いか)
第3部 開発・援助と日本の生い立ち(戦後日本は、なぜ援助に乗り出したのか;日本に援助庁がないのはなぜか;「日本モデル」はなぜ打ち出されなかったのか)
著者等紹介
佐藤仁[サトウジン]
1968年東京都生まれ。東京大学教養学部教養学科(文化人類学分科)卒業。東京大学大学院総合文化研究科博士課程(国際関係論)修了。ハーバード大学ケネディ行政学大学院修士課程(公共政策学)修了。学術博士。タイ政府政策アドバイザーを務めるなど実務経験もある。第10回日本学士院学術奨励賞、第28回大同生命地域研究奨励賞受賞。現在、東京大学東洋文化研究所教授・プリンストン大学ウッドロー・ウィルソンスクール客員教授。主著『稀少資源のポリティクス』東京大学出版会、2002年(2003年度国際開発学会学会賞、2003年度アジア経済研究所発展途上国研究奨励賞受賞)など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
とある本棚
afrisem
なーちゃま
ショウ
kk