内容説明
「オフサイドはなぜ反則か?」それは一生徒の素朴な問いから始まった。ゴールを目指しながらも、後ろへ後ろへとパスをつないでいくサッカーやラグビー。この不合理なルール“オフサイド”の発祥を遠い中世、英国の村祭りへとたどるとともに、このルールを愛し、育んできた英国の“こころ”を描く。「スポーツ・ルール学」を提唱する著者、渾心の作。
目次
序章 オフサイドとは何か(問題の所在;オフサイド・ルールの条件;オフサイドの適用 ほか)
第1章 オフサイド以前(分岐点;いろいろなフットボール;マス・フットボール ほか)
第2章 オフサイドの出現(生活感覚の変化;「校庭」の成立;「校庭のフットボール」の特徴 ほか)
終章 具体から抽象へ
著者等紹介
中村敏雄[ナカムラトシオ]
1929年、香川県生まれ。東京教育大学体育学部卒業。筑波大学附属高等学校教諭から広島大学教授などを務める。現在、『スポーツ評論』主幹
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
saga
56
【再読】フットボールはモブ(暴動)→空地→校庭へプレーのフィールドを変えながら洗練されていった。母国であるイギリスで、Footballと言いつつラグビー校式とアソシエーション式に分化していったのは興味深い。祭から競技へと変わってもなお、それを長引かせるための規則として、悪い振舞いであるオフサイドが成立したと言うが、数日間の競技が普通だった当時、なぜ競技を早く終わらせるようなプレーヤーが出てきたのかについては考察がされていない。日本の体育研究者が踏み込むには、あまりに奥深い問題だったのだろうか?2022/08/07
ころこ
36
もしサッカー(フットボール)にオフサイドの反則が無ければ、もっと多くの得点が入り、もっとゴールの瞬間に熱狂し、シーソーゲーム的な戦術的な多様さと観客的興味、何よりもゴールを見逃した観客により多くのゴールをみせることができる。のに、なぜフットボールはわざわざ得点の入らないオフサイドのような反則を設けるのか。著者が社会学や文化人類学の人ではない、体育教師としての実務家の側面が出ていて、体系的ではない一方で各章が短く平易なエッセイ風です。本書でも指摘されていますが、オフサイドの精神が最も顕著に現れているのはラグ2021/05/16
姉勤
29
題名のオフサイドがなぜ反則かを発端に、フットボール(サッカー、ラグビー他)の発祥から現代まで至る変遷を、時代を追って解説していく。フットボールは初め町(村)の住人総出の野戦の様な祭であり、数日に亘って楽しむ事を目的にし、ゲームを終わらせてしまう様な野暮な行為や卑怯な人間を「どこにも属さない(オフサイド)」とし忌み蔑んだことを発端にしていく...ほかにもトリビア的な情報も満載で、自分がスタジアムで感じる非日常感や帰属意識に感じていた事へ腑に落ちた一冊。サッカー好きなら読んで損は無い。2012/05/16
s-kozy
28
「オフサイドはなぜ反則か」このフットボールにおける根源的な問いを近代と現代のフットボールの成立過程に焦点を当てて解き明かしていく良書。粗暴性を内在しているこのスポーツで日本が上位に入り込めない理由を痛感した。下の世代にフットボールを伝えている人は本書で述べられていることは知っておくべきだろうな。2014/04/29
oldman獺祭魚翁
17
図書館本 あのラグビーWCの熱狂の中で特集として展示されていた本。ルールの本では無くイングランドで発展したフットボールの中で「オフサイド」(著者はこれを自分のチーム<サイド>から離れる<オフ>と言う意味だと書いている)というルールがいかにして出来たかという歴史を書いた本。フットボール全般の原型となるマス・フットボール(チームに分かれた百人以上で一つのボールを奪い合うもの)が19世紀のパブリックスクールを経て現在のラグビーやサッカーになって行ったかを考察している。面白い内容だがスポーツでは無く文化史の本2016/01/05
-
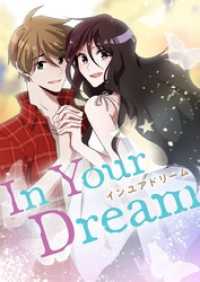
- 電子書籍
- In Your Dream【タテヨミ】…








