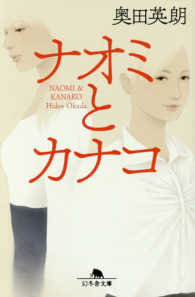内容説明
新聞と活字本の出現により、近代の文学空間はどのように形成されたのか。文学史に読者論を導くことにより、文化のなかに文学を位置づけ、文体のなかに時代を読みとる読者論の名著『近代読者の成立』に、後年のテクスト論に連なる諸論を集成する。
目次
近代読者の成立(天保改革における作者と書肆;明治初期戯作出版の動向―近世出版機構の解体;鴎外の中国小説趣味;明治立身出世主義の系譜―『西国立志編』から『帰省』まで;明治初年の読者像;音読から黙読へ―近代読者の成立;大正後期通俗小説の展開―婦人雑師の読者層;昭和初期の読者意識―芸術大衆化論の周辺;読者論小史―国民文学論まで;江戸紫―人情本における素人作者の役割;出版社と読者―貸本屋の役割を中心として;明治初期文人の中国小説趣味;露伴における立身出世主義―「力作型」の人間像;『賤のおだまき』考―『キタ・セクスアリス』の少年愛;近代文学と活字的世界;もう一つの『小説神髄』―視覚的世界の成立;『小説神髄』のリアリズムとはなにか;戯作文学と『当世書生気質』;ノベルへの模索―明耳21年前後をめぐって;言葉と身体;幕末・維新期の文体;明治の表現思想と文体―小説の「語り」をめぐって)
-
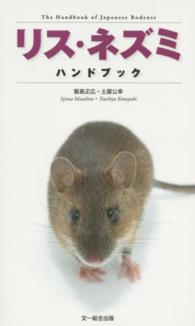
- 和書
- リス・ネズミハンドブック