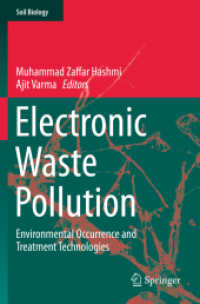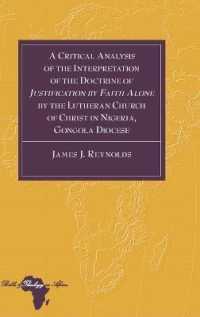内容説明
王は神を追放し、人はその王を、「人権」の名のもとに排除した。それは「人権」が、民族や宗教、国家すらも超えた、普遍的なものであると考えられたからである。その結果、「人権」に異を唱えるだけで差別主義とされかねない空気が広がり、私たちの日常生活は様々な混乱に見舞われている。「人権」の歴史をたどりながら、それが生み出しつつある転倒した現実を解明し、新たな視点を提示する。
目次
第1部 「人権」という考えはどう作られたか(「権利」はいつ生まれたか;「人権宣言」という虚構)
第2部 現代日本の「人権」状況(「人権」が無軌道な子供を作り出す;「人権」が家族の絆を脅かす;「人権」が女性を不幸にする)
著者等紹介
八木秀次[ヤギヒデツグ]
1962年広島県生まれ。早稲田大学法学部卒業。同大学院政治学研究科博士課程中退。専攻は憲法学、思想史。現在、高崎経済大学助教授。一貫して「保守主義」の立場からなされる議論は、論壇の注目を集めている
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
NICK
11
保守系思想というのは少し苦手なのだが、読んでみるとやはり苦手意識が高まってくる。普段我々があたかも自明であるかのように用いがちな「人権」の概念がその実、西洋という限定的な風土の歴史的産物であることを論じ、フランス革命以来の「人権」というのは地域や社会、伝統に根ざさない(暴走リスクを抱える)「負荷なき個人」でしかない、と断じる。保守系人権論の定番で目新しさは余りない。保守派を知る教科書の一つとしていいかもしれない。ところで「子どもの凶悪犯罪の増加」を憂いているが、2014年現在、少年犯罪は減少傾向にある。2014/12/10
かず
7
この本は凄い!今年一番の感動を覚えた!ただ、残念なのは、良著なのに、この題名にピンと来る人はそうはいないだろう、ということ。なぜなら、「『人権』とは、絶対的に是」と皆が思い込んでいるからである。私は「常識を疑うこと」を大切に思っている。如何なる崇高な思想も、生み出した思想家と同程度に思考し実践しなければ理解できず、一挙に陳腐化してしまう。そして、そこにはただ空虚な言葉が残るのみである。人権思想を突き詰めると、個人主義に行き着く。しかし、何にも影響を受けない自由人などありえないことは、仏教国の日本人(→)2015/07/12
乱読家 護る会支持!
4
「人権」とは「人間の権利」の略であり、丸裸の「個人」に還元した上で、それが有する「権利」である。 誰にでも、あらゆることが平等に与えられるという意味では無い。各々が正しいと思うと事を社会の正しさにするために闘う権利である。 つまり「人権が守られていない」との文脈で政治行動することは、意味合いとしては間違っていて、正しくは「〇〇の不公平を解消せよ」と具体的な要求を掲げて行動すべきである。 そして、そのことに違和感がある人は、「その考え、要求はおかしい」と自己主張する「人権」を行使すべきである。2021/08/27
大ふへん者
4
「人権」概念の正当性に疑問がある方は一読してみると良いかもしれない。イギリスのコモンロー時代からの変遷が一望できる第一章は、古今の思想家による是非が整理できる。やはりマルクス=バディウ的な批判がしっくりくる。「人権」が想定するような歴史・伝統・文化などから切り離された抽象的な個体(主体)などありえないだろう。第二章以降は保守論者らしく、教育によって子供から家族へ社会へと人権イデオロギー浸透し崩壊するというお話。個人的にはやや中立性を欠く議論で面白くなかったし強引に結論付けたいだけな気がした。2014/08/06
肉欲棒太郎
2
人権という概念の成立史をたどった第一部『「人権」という考えはどう作られたか』は勉強になり面白かったが、第二部『現代日本の「人権」状況』は、夫婦別姓批判とかフェミニズム批判とかの、まあありがちな保守派のサヨク批判という感じで特に面白くもない。領土問題で諸外国に強い態度で臨むためには「権利」意識が重要になるが、一方で個人の「権利」意識は共同体の伝統的価値観を脅かすものにもなりうるという、保守派にとってのジレンマがうかがい知れて面白い。2017/03/06
-
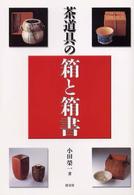
- 和書
- 茶道具の箱と箱書