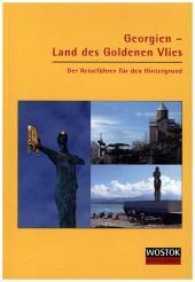出版社内容情報
会話的推意の理論など、主に言語哲学の業績で知られるポール・グライス。その素顔と広範な射程を持つ哲学の全体像を初めて描き出す。
会話的推意の理論と非自然的意味の分析の哲学者として知られるグライスは、心の哲学、理性論、形而上学といった分野でも多くの業績を持つ。その哲学体系を貫くのは、理性というテーマである。グライスにとって、理性は推論の能力であるとともに、理由を与える能力でもあった。歴史的な背景とともに、その哲学体系を一望のもとに描く。
内容説明
会話的推意の理論や意図基盤意味論などによって知られ、言語哲学や語用論に大きな影響を与えたポール・グライス。心の哲学・理性論・形而上学を含む幅広い射程を持つその哲学体系が「理性」というテーマに貫かれていることを指摘。その素顔と哲学の全体像を初めて描き出す。
目次
第1章 グライスの生涯
第2章 日常言語に目を向ける
第3章 会話的推意の理論
第4章 会話的推意の理論とは何なのか
第5章 「言う」と「意味する」
第6章 心理と行為
第7章 理性と幸福
第8章 形而上学と超越論的論証
著者等紹介
三木那由他[ミキナユタ]
1985年神奈川県に生まれる。2013年京都大学大学院文学研究科博士課程指導認定退学。2015年博士(文学)。現在、大阪大学大学院文学研究科講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
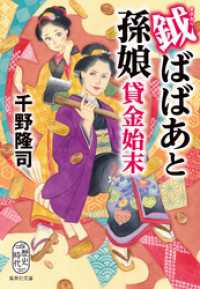
- 電子書籍
- 鉞ばばあと孫娘貸金始末 集英社文庫
-
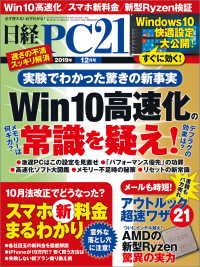
- 電子書籍
- 日経PC21(ピーシーニジュウイチ) …