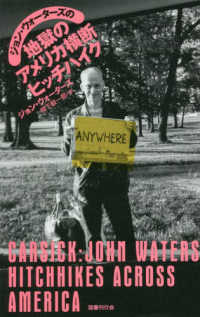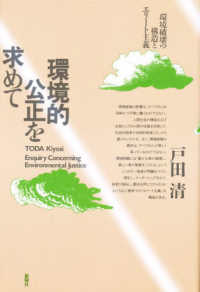出版社内容情報
《内容》 なぜ患者さんの右側から診察を行なうの? なぜ頸静脈をアセスメントすることで、右心不全が見抜けるの? フィジカルアセスメントの「なぜ」を解決しながら、基本的知識と技術を解説するガイドブック。目的と根拠がわかれば、フィジカルアセスメントは看護につながる。
《目次》
Part1 症状・徴候からのアセスメント
1. 頭が痛い
2. 胸が痛い
3. お腹が痛い
4. 息苦しい
5. ドキドキする
6. 咳が出る
7. むくみがある
8. 口から血が出た
9. 気を失った
10. フラフラする
11. しゃべりにくい
12. 見えにくい
13. 思ったように身体を動かせない
14. おしっこの調子が悪い
Part2 身体機能別のアセスメント
A. 呼吸系
1. 胸部における「場所」を表す(1)-水平位置(肋骨・肋間)の同定
2. 胸部における「場所」を表す(2)-垂直位置の同定
3. 胸壁と肺との関係を捉える
4. チアノーゼの有無を確認する
5. ばち状指の有無を確認する
6. 触診により呼吸の観察をする
7. 視診により呼吸の観察をする
8. 触覚振盪音(音声伝導)を確認する
9. 胸郭を打診する
10. 横隔膜を同定する
11. 呼吸音を聴取する
12. 呼吸音を評価する
B. 循環系
1. 脈を触知する
2. 血圧を測定する
3. 頸静脈により中心静脈圧を推定する
4. 心臓の大きさを推定する-心尖拍動の触知
5. 心音を聴取する(1)-I音とII音を聴く・聴き分ける
6. 心音を聴取する(2)-過剰心音の有無を確認する
7. 心音を聴取する(3)-心雑音を聴き取る
8. 心音を聴取する(4)-心音の正常・異常を判断する
9. 末梢循環不全を評価する(1)-動脈の循環を確認する
10. 末梢循環不全を評価する(2)-静脈の循環を確認する
C. 消化系
1. 口から食物を摂取できるかを評価する
2. 咽頭反射をみる
3. 腹部のアセスメントを行う
4. 腹部を視診する
5. 腸蠕動音の消失・減少を判断する
6. 肝臓の大きさを推定する
7. 腹水の有無を判断する
8. 腹部を触診する
D. 感覚系
1. 眼位の異常の有無をみる
2. 外眼球運動を確認する
3. 視力・視野をスクリーニングする
4. 聴力をスクリーニングする
5. 伝音性難聴/感音性難聴を鑑別する(1)-リンネ試験
6. 伝音性難聴/感音性難聴を鑑別する(2)-ウェーバー試験
7. 皮膚知覚(痛覚・触覚)をみる
8. 深部感覚(振動覚)を評価する
E. 運動系
1. ADL・歩行を観察する
2. 関節可動域を測定する
3. 筋力をスクリーニングする
4. 筋力を測定する
5. 小脳機能を評価する
6. 平衡機能を評価する
F. 中枢神経系
1. 意識状態を測る
2. 呼吸パターンを確認する
3. 瞳孔および対光反射を確認する
4. 脳幹反応をみる
5. 高次脳機能を評価する(1)-認知症のアセスメント
6. 高次脳機能を評価する(2)-失語のアセスメント
参考文献
索引
目次
1 症状・徴候からのアセスメント(頭が痛い;胸が痛い;お腹が痛い;息苦しい ほか)
2 身体機能別のアセスメント(呼吸系;循環系;消化系;感覚系 ほか)
著者等紹介
山内豊明[ヤマウチトヨアキ]
1985年新潟大学医学部医学科卒業。1991年同大学院博士課程修了、医学博士。内科医・神経内科医として通算8年間の臨床経験の後、カリフォルニア大学医学部勤務。1996年ペース大学看護学部卒業、米国・登録看護士免許を取得。1997年同大学院看護学修士課程修了、米国・診療看護師(ナース・プラクティショナー)免許取得。1998年ケース・ウェスタン・リザーヴ大学看護学部大学院博士課程修了、看護学博士。同年に帰国し、大分県立看護科学大学助教授に就任。1999年看護士、保健士免許取得。2002年より名古屋大学医学部基礎看護学講座教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 和書
- 楽しい数学 (第2版)