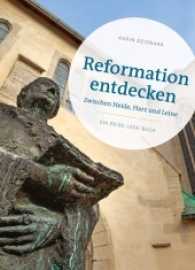出版社内容情報
酸鼻を極めた店名の大飢饉を皮切りに、農村・都市を通じての動揺は一段と激しくなる。幕府も諸藩も必死だが、崩れゆく封建制は如何ともできない。〈解説〉藤田覚
内容説明
改革の情熱に燃えた松平定信が退いたのち、将軍家斉は大奥に退廃と爛熟の生活を送り、町人は“いき”をてらう。折しも近海に出没する異国船は目を辺境に向けさせ、伊能忠敬・近藤重蔵・間宮林蔵らの活躍を生むが、先覚者はまだ変革の夢を次代に託さねばならなかった。
目次
天明の大飢饉
松平定信の登場
足の裏までかきさがす
農村復興
米価調節と御用金
諸国国産品
海防と探検
もとの田沼に
博徒と八州廻り
三都の町人
大御所の生活
大江戸の文化
国学と洋学
草莽の文化
天保改革の前夜
士農工商おののくばかり
上知令と軍事改革
雄藩の擡頭
著者等紹介
北島正元[キタジママサモト]
1912(大正元年)、新潟県に生まれる。35年(昭和10)、東京帝国大学文学部国史学科卒業後、鳥取青年師範学校教授、50年に新潟大学助教授、51年より東京都立大学助教授、59年同大教授、76年名誉教授となる。その後、立正大学教授、早稲田大学客員教授を務める。83年逝去。専攻は日本近世史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
84
天明の大飢饉から、田沼政治への批判が起こって松平定信が政権の中枢につきます。それまでの田沼派とのやり取りやその後の田沼派の復活などは物語としても面白く、佐伯泰英さんの小説よりも楽しめそうです。また江戸の文化や庶民の生活なども活写されていて楽しめます。「通」から「いき」へと変わったのもこの時代だそうです。2015/10/15
穀雨
6
松平定信の寛政の改革から黒船前夜までの江戸時代後期がテーマ。『元禄時代』や『町人の実力』といった前巻に比べると筆致がやや生硬で、シーボルトを密訴した間宮林蔵について「しょせん保守・固陋の一幕吏に過ぎなかった」(p402) と述べるなど、辛辣な評価も散見される。その点、時代の行き詰まりといった雰囲気が濃厚に感じられるが、文化や産業面については町人を中心とする庶民の活躍を生き生きと伝えていて、庶民の台頭という時代の大きな流れが浮き彫りになっていた。2021/03/28
あしお
4
寛政の改革と天保の改革辺りを扱う。松平定信も水野忠邦も優秀だけど人の気持ちが分からない感じの人ですね。「民を豊かにする」ために「贅沢を禁じる」って物凄い矛盾を感じるのですが^_^;。最も最近でも経済を立て直すために経費削減をしていたけれど。。儒教は個人的にはとても好きで四書はもちろん近思録も素晴らしいと思うのだが、なんで儒者っていうのはおかしな人が多いのだろう。正義中毒を起こすのかな。2020/10/14
takeshi3017
3
中央公論の歴史本第18巻。老中は松平定信~水野忠邦。田沼失脚後の松平定信の質素倹約を特色とする寛政の改革、家斉の大御所時代を経て、水野忠邦の天保の改革へと時代は進む。その間飢饉があり、打ちこわしや一揆も多発。為政者たちは農村の荒廃を防ぎ、米価や物価の対策に金の含有量を変えたり、株仲間を奨励or解散させたりと様々な方策を試みるが、それらの改革は吉宗の享保の改革ほどには効果が出なかったようである。詳細→ https://takeshi3017.chu.jp/file9/naiyou33201.html2023/08/12
kenitirokikuti
3
大正の米騒動と大塩の乱を比べる。「米価調節と御用金」寛政から文文まで、米価は下がり、他の物価は上がる。天保には大飢饉で米価が高騰。大坂の物資取扱量の減少についてはリンクさせていない2016/10/16
-

- 洋書
- SUR' VIVANTE