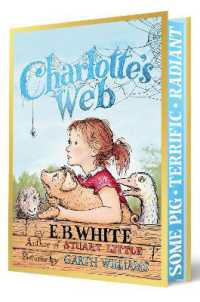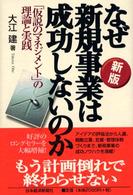内容説明
本書は、「軍法務」の観点から、これまでの政治史や戦史で描ききれなかった「挙国一致」体制への道程をかいまみ、戦争の実態を解析する。
目次
1 「事変」であって戦争ではない―なぜ「事変」なのか
2 戦争と称しなかったために―「事変」とされたことの意味
3 「事変」は事実上の戦争である―戦時体制の整備
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
114
海軍法務局の手になる「海軍司法法規より見た事変という意味」の事変関係の法規について行った解釈と運用上の指針が収められている資料をもとにこの本が書かれていてよくまあこのような資料が遺されていたものだと思います。海軍だから遺したのかもしれません。時期は昭和12年7月の盧溝橋事件から14年1月の近衛内閣総辞職までの時期を書かれています。きちっとこのような分析あるいは解釈をしているということは、陸軍よりもまともな人間が多かったということなのでしょうか?2016/05/07
おらひらお
5
1994年初版。結構難しいところもありますが、基本的に戦争は無法でやっているのではなく、法に則って対応していることを知りました・・・。あと、戦争ではなく事変とした理由も法の解釈によるものでしたね。ちなみに後半では秘密関連の話も。日中関係もなんだか変な感じになっていますが、そういう意味ではタイムリーなものでした。2013/11/29
印度 洋一郎
4
海軍法務局の資料から、支那事変初期の法的側面を見る。戦争ではなく事変なのは、日中双方が国際法上の戦争という扱いにデメリット(主に物資の供給)を感じていたからだが、そのために日本は中国へ第三国の支援を止める事に制限があり、その対策(海軍の場合は海上封鎖)に追われた。その辺りの法解釈から、事変の長期化で銃後の家庭のトラブルを防止するための民事的な法令(裁判所による仲裁)、増加する兵士の犯罪への対応、前線や内地での流言飛語の取締等、様々な法的動きがあった。アナーキーなようで官僚組織だった日本軍の一側面もわかる2016/12/13
wei xian tiang
2
書題からは盧溝橋事件を扱った本のように思われるかもしれないが,事変下軍法務の考え方を追った好著。殊に,占領下司令官の軍令として非軍人非邦人に適用する「軍律」については,戦後殆ど等閑視されていたのでは。2018/05/09
Gen Kato
2
宣戦布告がないままはじめられ、「事変」として拡大していく中国での戦火。実際の法的処理は「戦争」として行なわれていた。こうした言葉のすりかえは今でも政治家がよくやっているトリックで、施政者のやり口は変わっていないのだなあ。「軍律法廷」が興味深かった。2015/05/08