出版社内容情報
40歳の植木職人・坂井祐治は、十数年前の災厄によって仕事道具を全てさらわれ、その2年後、妻を病気で喪う。自分を追い込み肉体を痛めつけながら仕事に没頭する日々。息子との関係はぎこちない。あの日海が膨張し、防潮堤ができた。元の生活は決して戻らない。なぜあの人は死に、自分は生き残ったのか。答えのない問いを抱え、男は彷徨い続ける。止むことのない渇きと痛みを描く芥川賞受賞作。
内容説明
40歳の植木職人・坂井祐治は、十数年前の災厄によって仕事道具を全てさらわれ、その2年後、妻を病気で喪う。自分を追い込み肉体を痛めつけながら仕事に没頭する日々。息子との関係はぎこちない。あの日海が膨張し、防潮堤ができた。元の生活は決して戻らない。なぜあの人は死に、自分は生き残ったのか。答えのない問いを抱え、男は彷徨い続ける。止むことのない渇きと痛みを描く芥川賞受賞作。
著者等紹介
佐藤厚志[サトウアツシ]
1982(昭和57)年、宮城県仙台市生れ。東北学院大学文学部英文学科卒業。2017(平成29)年、「蛇沼」で新潮新人賞を受賞しデビュー。’20年「境界の円居」で仙台短編文学賞大賞を、’23(令和5)年『荒地の家族』で芥川賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
absinthe
94
生きるっていうのはつらい事でもあるんだな。大災厄の日の後、生き残った人々の話。生存者は自分が生き残ったことに罪悪感を感じることもあるらしい。死んでいった人に申し訳ないと思うような。自分を辛い環境に押し込んで、自らを罰しているような。そんな姿が描かれる。2025/09/30
A.T
30
また、海の町なのだ。以前読んだ村上春樹の短編小説「アイロンのある風景」(1999年)にも浜辺で焚き火する男が震災後の神戸の家族を思うシーンで、炎を見つめる時の心癒される情景が描かれていた。佐藤厚志「荒地の家族」の主人公は東日本大震災で傷ついた人々とのふれあいを描くなかにも、海岸で一斗缶の焚き火をする男が描かれている。焚き火のはぜる音と匂い、炎を媒介にして傷ついた人が失ったものを弔うのだろうか。それぞれの失意は語らないし、尋ねない。春樹の人物が饒舌であったのに、ここでは無口なのが東日本らしさなのかも。2025/06/17
桜もち 太郎
23
終始暗く救いようのない物語。解説の小川洋子さんは主人公祐治の息子が最後に笑うところが、光が見えると書いていたが、自分にはそうは見えなかった。東日本大震災を生き延びた家族だが、彼の妻は2年後に流感にやられ死んでしまう。再婚した相手との間にできた子供は流産。その妻にも逃げられる。「どれだけ土をかぶせてもその穴は埋まらない」「この世にはまだ見ぬ、計り知れなぬ災厄が順番を待っている不吉な予感があった」。震災を経験した人たちの心情なのかもしれない。幼馴染の明夫の自殺が決定的だった。元の生活には戻ることはできない。→2025/07/02
ホシ
18
造園会社から独立した祐治は、歴史的厄災で仕事道具を失う。その2年後には病気で妻・晴海までも失う。旧友の紹介で知加子と再婚するも彼女の流産を機に離婚へ。立て続く喪失の虚無感に苛まれつつ晴海との息子・啓太の面倒を見るが息子との関係はぎこちない。かつて、晴海に思いを寄せていた幼馴染の明夫には「報いだ」とまで言われ…。▽2026年の目標はもっと文学を読むこと。良い読書が出来ました!解説にあるように喪失と「再生」なんていう言葉を安易には使いたくない作品です。『黒い雨』のような災厄を記録に残す良作です。2026/01/13
cao-rin
15
初めての作家さん。第168回芥川賞受賞作。東日本大震災で仕事道具全てを波にさらわれ、2年後には妻を病で亡くした40歳の植木職人・祐治を中心とした物語。震災によって大きく人生が変容し、何とか再生をめざすが、お世辞にも前向きな話ではなく、どの人も痛みや苦悩を抱えたまま日々を生きる。復興とか、再生とか、そんな表面的な言葉では表現できないし、恐らくゴールなどない。それでもほんの一筋の光や平穏が、被災者の方々の元に少しでも多く訪れて欲しいと願わずにいられない。2025/06/20
-
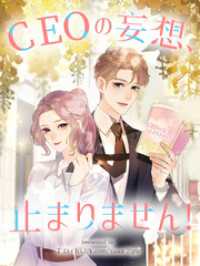
- 電子書籍
- CEOの妄想、止まりません!【タテヨミ…
-
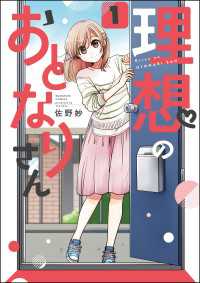
- 電子書籍
- 理想のおとなりさん(分冊版) 【第1話…






