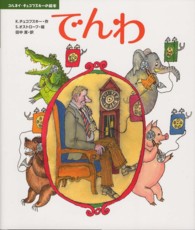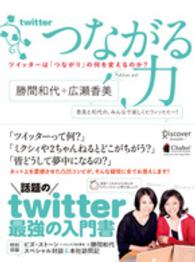出版社内容情報
それでも「少年」は守られるべきか
少年による凶悪犯罪が跡を絶ちません。統計によると少年犯罪は減り続けていますが、猟奇的な事件や、いわゆる体験殺人――人を殺してみたかったから殺した――など、動機が不可解なケースは、むしろ増えている印象があります。一方で、少年(未成年)、とくに18歳未満は少年法で手厚く守られており、重罪を犯して刑事裁判にかけられても短期間で出所するケースがほとんどです。遺族たちは口をそろえて「これでは無駄死にだ」「なぜ死刑や無期懲役にできないのか」と憤慨しますが、少年法の壁は厚く、犯した犯罪と量刑が釣り合っているとは言えません。
また、遺族に対する加害者側の対応も、ひどいケースが目立ちます。一言の謝罪もない、追い打ちをかけるような言動をする、民事裁判で決まった損害賠償を支払わない……挙げ句の果てには再犯を繰り返し、また罪に問われている元犯罪少年も少なくありません。本書では、少年凶悪犯罪の遺族たちに綿密な取材を重ね、そうした実態を明らかにするとともに、少年と少年法の罪について深く考察します。
【編集担当からのおすすめ情報】
1948年に成立した少年法は4度改正され、そのたびに厳罰化の方向に向かっています。しかしまだ遺族たちが満足するレベルには至っていないし、少年による凶悪犯罪は発生し続けています。「酒鬼薔薇聖斗」に触発されたのか、猫などの動物を殺す事件も頻発しており、不穏な雰囲気が漂っています。
選挙年齢の引き下げにともなって、少年法も改正されるとは思いますが、刑罰は年齢だけを基準にしていていいのでしょうか。少年院などの矯正プログラムは、本当に機能しているのでしょうか。
この本がそれらのことを考えるきっかけになれば幸いです。
内容説明
“厳罰化”が進められ、被害者側の権利も拡大してきた少年法。しかし、まだ殺人事件の遺族が納得できるレベルではない。また、民事裁判で損害賠償が認められても、履行を強進する術はなく、加害者の“逃げ得”にあうことも多い。少年によって我が子の命を奪われた被害者遺族たちは、どうすれば“救われる”のか、何を望んでいるのか―。長年にわたる遺族への取材を通じ、ほとんど知られることがなかった少年審判の実態、「謝罪と贖罪」の現実に迫る。
目次
第1章 短すぎる「不定期刑」の罪(「川崎中一男子生徒殺害事件」の現場;息子が最後に見た風景 ほか)
第2章 殺人を犯した少年が再び犯行に及んだわけ(再び事件を起こした元殺人犯;人を殺しても重罪には問われないという不条理 ほか)
第3章 「贖罪」に終わりはない(前触れもなく「謝罪」にあらわれた加害者;眼球が飛び出るほどの激しいリンチ ほか)
第4章 「賠償」の意味を考える(些細な理由で始まった集団リンチ;「あなたたちの息子がやったことを、目に焼き付けておきなさい」 ほか)
第5章 少年法と実名報道(「人を殺してみたい」という衝動が止まらない;前兆は、すべて見過ごされた ほか)
著者等紹介
藤井誠二[フジイセイジ]
1965年、愛知県生まれ。高校卒業後、本格的にノンフィクションライターとして活動を開始。教育問題、少年犯罪、沖縄問題等について精力的に作品を発表、テレビやラジオ等でも提言している。とくに犯罪被害者遺族問題については、その綿密かつ、当事者の声を真摯に聞く取材に定評がある。愛知淑徳大学の非常勤講師も務める(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
- 評価
購入済の本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ゆみねこ
GAKU
mana
鈴
リキヨシオ


![iPhone 13 Pro/13 Pro Max/13/13 mini便利すぎる [テキスト]](../images/goods/ar2/web/imgdata2/48663/4866365226.jpg)