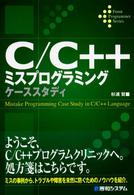出版社内容情報
「つかう」を巡る、かくも深く、多様な論考
「つかう」という言葉の様相をさまざまな観点から考え抜いた一冊。道具をつかう、出汁につかう、楽器をつかう……、同じ「つかう」でも、その意味はさまざま。この単語を契機に、意味を探り、使われ方の変遷を辿り、哲学はもちろん、民俗学、芸術学、料理本まで関係書物を渉猟し、考えを深めていきます。著者は、2015年4月から朝日新聞の朝刊に「折々のことば」を連載中の、現代哲学の第一人者である鷲田清一氏。「つかう」を巡り、ひとをつかうから始まり、道具の使用、民芸での意味の変遷、多種多様な身体用法、武道でのかけひき、保育・介護の場面での展開、ペットとのつきあい、ひとと楽器の関係など具体的な場に即して、徹底的に考え抜いた哲学エッセイで、鷲田ワールド全開の一冊です。ひとを、道具を、楽器を、衣服を、ペットを……、「つかう」を介して人はどのように、ひとと、社会と、世界と拘わっているのかを深く考察します。カバー写真と文中には、現代写真の先端で作品を発表し続ける、ヴォルフガング・ティルマンスの写真を採用。アートにも親和性の高い一冊です。
【編集担当からのおすすめ情報】
「折々のことば」の筆者が、短い論考では追い切れない、徹底的に考え抜いた「つかう」を巡る一。ヴァルフガング・ティルマンスのカバー写真も、日本の書籍に初採用。ハッと眼をひく装幀です。
内容説明
「使う」「使われる」広やかな意味を持つ「つかふ」をもういちどわたしたちの暮らしにたぐり寄せる。
目次
1 「つかふ」の原型(「つかふ」という事態;身体の用法 ほか)
2 技倆―“用の美”から“器用仕事”へ(「用」と「美」;技巧・技術・技倆 ほか)
3 使用の過剰―「使える」ということ(「使える」ということ;反動に応じる ほか)
4 「つかふ」の諸相(スケッチ)(遣ふ;飼う その一 ほか)
5 使用の両極(いたぶり;占有 ほか)
著者等紹介
鷲田清一[ワシダキヨカズ]
1949年、京都生まれ。京都大学大学院文学研究科(哲学)博士課程修了。大阪大学教授、同総長、京都市立芸術大学理事長・学長等を経て、現在、せんだいメディアテーク館長、サントリー文化財団副理事長。主な著書に『モードの迷宮』(サントリー学芸賞)、『「聴く」ことの力』(桑原武夫学芸賞)、『「ぐずぐず」の理由』(読売文学賞)など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
けんとまん1007
抹茶モナカ
amanon
pppともろー