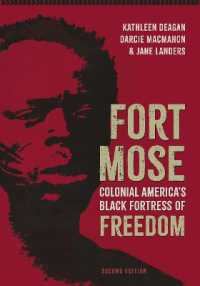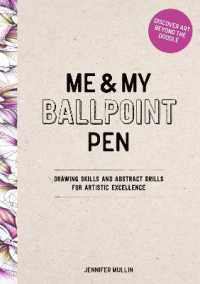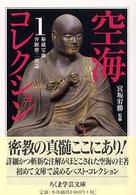出版社内容情報
國分 功一郎[コクブン コウイチロウ]
著・文・その他
内容説明
次々と覆される常識の先に、ありえたかもしれないもうひとつの世界が浮かび上がる。気鋭の哲学者による、心揺さぶる倫理学入門。
目次
第1章 組み合わせとしての善悪(スピノザとは誰か;哲学する自由 ほか)
第2章 コナトゥスと本質(コナトゥスこそ物の本質;変状する力 ほか)
第3章 自由へのエチカ(「自由」とは何か;自由の度合いを高める倫理学 ほか)
第4章 真理の獲得と主体の変容(スピノザ哲学は「もうひとつの近代」を示す;真理は真理自身の基準である ほか)
第5章 神の存在証明と精錬の道(懐疑の病と治癒の物語;真理への精錬の過程 ほか)
著者等紹介
國分功一郎[コクブンコウイチロウ]
1974年、千葉県生まれ。東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。博士(学術)。東京大学大学院総合文化研究科・教養学部准教授。専門は、哲学・現代思想。著書に、『暇と退屈の倫理学』(朝日出版社、第二回紀伊國屋じんぶん大賞受賞、増補新版:太田出版)、『中動態の世界』(医学書院、第一六回小林秀雄賞受賞)、『原子力時代における哲学』(晶文社)など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
mukimi
127
筆者の代表作「暇と退屈の倫理学」で出会ったスピノザ哲学が魅力的で本書を。人の中には存在しようとする力がありその力こそが本質でありその力は経験の組み合わせにより上下するすなわち倫理学は個別の実験を要する、という私的性、さらに、自由/能動/真理の獲得を「(過程の中の)度合い」で捉える大らかさが(真理を公共的で確固たるエビデンスと定義したデカルトと対峙される)スピノザ哲学の特徴らしい。スピノザが実際、喜びを生み出す組み合わせを実験しながら追求し釣りや音楽など刺激の幅を広げる生き方をした、という点が興味深い。2023/12/11
ちくわ
104
【♪】『スピノザの診察室』に感銘を受けたので、ミーハー心が爆発しエチカを読んでみたくなる。ただ、あまりに難解との話なので、まずは入門書である本書を手に取ってみた。感想…全然理解出来ていないが、個々人に優しく温かい哲学だと感じた。また、ダ・ヴィンチの偉業やデカルトの方法序説をふと思い出してしまう…ダ・ヴィンチ、デカルト、そしてスピノザ…本質に迫れる稀代の賢人には、文系や理系などの線引きは無意味なのかもね。彼らにはどんなジャンルの学問も、未知なる事象を解明しようとする試みとして同じように捉えていたのかもなぁ。2025/12/22
ひろき@巨人の肩
104
1677年出版のスピノザ著『エチカ』が説く「自由」が現代人の道標となる。デカルト哲学「我、思う故に我あり」を起点に発展した近代哲学。個々人の「自由意志」を原動力に発展した資本主義社会と科学技術。その結果、形成された高度な情報化社会と求められる持続可能な社会。これらに適応するために「自由」を再定義する時期に来た。スピノザ哲学における「自由」とは、世界がもたらす不合理な「強制」から脱却する「力」の獲得。そのためには、物を知り、自分を知り、実験することで、自分を変えていくしかない。2023/11/13
アキ
102
スピノザの先祖はスペイン系ユダヤ人で迫害のためオランダに渡った。ベントー・バールーフ・ベネディクトと、ポルトガル・ヘブライ・ラテン語の名を持つ17世紀の哲学者。デカルトは近代科学の元であるが、主体の変容がなく存在を単なる認識の対象とした。スピノザの汎神論・神即自然・自由・主体の変容と著者の言う「違うOS」を分かりやすい例えで論じており理解できる。現代の脳科学で証明されているように、意志を持つ前に行為が開始されていることは「神という実体が変性して様態が生まれる」という考えに合致する。知的興奮が得られる一冊。2021/05/15
venturingbeyond
88
NHK『100分 de 名著』のテクストに、新たに1章を加えて新書としたスピノザの入門書。スピノザといえば、高校倫理の教科書では、「汎神論」や「神即自然」、「心身並行論」といった中心概念が、定義や説明もなく記述され、履修者は訳も分からず経文のように丸暗記させられるというのが相場(まったくスルーの場合もあるので、扱うだけ良心的なのかも...)。しかし、この国分先生の著作は、初めてスピノザに触れる初学者にも、その勘所を平易に伝える良質の入門書。2020/12/28


![The Reason Why. Domestic Science [by R.k. Philp]](../images/goods/../parts/goods-list/no-phooto.jpg)