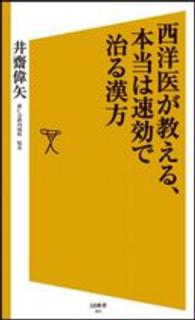出版社内容情報
唐の時代、関係諸国中、最も地位が高いのは吐蕃、では日本は? 東アジア論、冊封体制論など歴史学の枠組みそのものを問い直す一冊。
南に農耕王朝、北に遊牧王朝という大帝国があり、その周辺に
複数の小帝国が存在していた国際環境において、日本が採用した外交政策とは?
「倭の五王」期の朝鮮半島問題、「日出ヅル処ノ天子」時代の隋の絶域外交、
乙巳の変の背景にある国際緊張など、外交文書、外交儀礼を丹念に読み解き、
四世紀から一三世紀にいたる東部ユーラシアと古代日本の実像に迫る。
序章 日本と中国への視線
第一章 東アジアと東部ユーラシア
第二章 第二次南北朝時代と平安期日本
第三章 倭の五王と第一次南北朝時代
第四章 唐の全盛期と日本律令制の成立
第五章 律令制国家と東部ユーラシア
終章 新たな世界史像の模索
内容説明
南に農耕王朝、北に遊牧王朝という大帝国があり、その周辺に複数の小帝国が存在していた国際環境において、日本が採用した外交政策とは?「倭の五王」期の朝鮮半島問題、「日出ヅル処ノ天子」時代の隋の絶域外交、乙巳の変の背景にある国際緊張など、外交文書、外交儀礼を丹念に読み解き、四世紀から一三世紀にいたる東部ユーラシアと古代日本の実像に迫る。
目次
序章 日本と中国への視線
第1章 東アジアと東部ユーラシア
第2章 第二次南北朝時代と平安期日本
第3章 倭の五王と第一次南北朝時代
第4章 唐の全盛期と日本律令制の成立
第5章 律令国家日本と東部ユーラシア
終章 新たな世界史像の模索
著者等紹介
廣瀬憲雄[ヒロセノリオ]
1976年岐阜県生まれ。名古屋大学文学部卒業。同大学大学院文学研究科博士後期課程修了。名古屋大学高等研究院特任助教などを経て、愛知大学文学部准教授。専攻は日本古代史、東アジア対外関係史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
四四三屋
Takashi
さとうしん