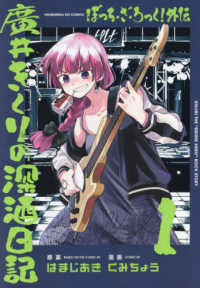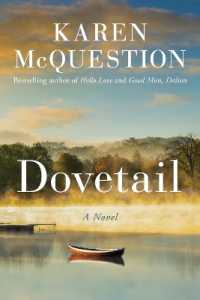内容説明
恐慌と戦争、廃墟からの再建、高度成長を経てバブル経済に至る時期まで、社会のめまぐるしい激変と経済の実態はどう関連していたか。現在の日本経済の構造はいかにして形成されたのか。経済史の第一人者が時代の変動に向き合いつつ、堅実なデータ分析と説得的な歴史観で変化と連続の両側面を把握した最良の入門書。
目次
第1章 恐慌のなかの変容―一九二〇年代
第2章 バターも大砲も―一九三二‐三七年
第3章 戦争の爪痕―一九三七‐四五年
第4章 廃墟からの再建―一九四五‐五一年
第5章 「強兵」なき「富国」―一九五二‐六五年
第6章 「経済大国」―一九六六‐七五年
第7章 古典的経済への回帰―一九七五年以後
著者等紹介
中村隆英[ナカムラタカフサ]
1925年生まれ。東京大学名誉教授。専攻=日本経済史。東京大学、お茶の水女子大学、東洋英和女学院大学で教授を務めた(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kawa
28
図書館特集コーナーで目に留まる。昭和初期の金本位制復帰のあれこれについて基本が知れたことが第一の収穫。私が社会に出た直後の経済情勢、オイルショック、狂乱物価騒ぎ、戦後最大不況、為替変動相場制170円の円高、第2次オイルショックと激動の時代だったことを改めて確認というか、ビックリ。あの頃、そんなことにも関心がなくて平々凡々と生きていたことが不思議。この時代の先達は省エネ(製造業のエネルギーコストは10年で約40%削減)や、素材産業から高付加価値産業への転換を図っていたという。本書は昭和60年まで。2025/02/19
Z
7
分かりやすかった。今まで読んだ経済史の本で一番良かったかもしれない。経済状況、それに対する政治、政策、法案等の対処が丁寧に描かれ、特に戦争期の力学が読ませたし、現在にも応用して各国の経済政策等、どんなことを考えているかが分かるように経済学の知見もしっかり書かれていた。叶わないが、この人による平成の経済史も読みたかった。明治の頃から、いわゆる保守派のほうがケインズ政策をおこない政党の力に結びつけたという構図があったり、戦争期の計画経済が戦後の経済の構図を決定づけるも、高度経済成長後、産業界も力をつけオイルシ2018/02/03
ぜっとん
1
読みやすいし判りやすい。そしてよくまとまっている。ど素人でもかなり楽しく読めた。特に戦争は突然起こって突然世の中をがらりと変えたというわけでなく、戦争の起こるシチュエーションが準備され、また戦時下においても戦後の成長へ繋がる要素が準備されていたという点を、経済という側面からたいへん平易にかつダイナミックに語っている点が特に興味深かった。2012/11/29
Lulo
0
公務員試験対策のために。ですます調だったりそうじゃなかったりが最初気持ち悪かったけど、総じて初心者の大学生にも読みやすい。経済学面白いな、と思わせてくれた大切な一冊。読んでよかった!2016/05/18
隠居
0
講演体なので読みやすい。戦後の復興が戦中に蓄積した技術によっていること、戦後まもなく農村農業人口が増大したこと、つまり村に若者が多く活気があったこと、オイルショックに合理化で耐えた経済界が今度は行政に合理化を求めたこと、など啓発された。2012/11/13
-

- 和書
- しのび草