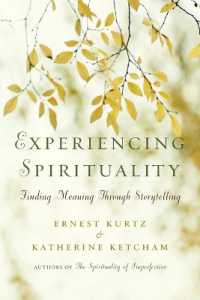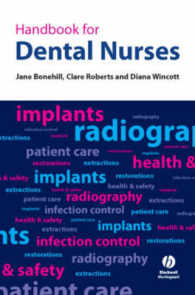出版社内容情報
ゆたかな経済生活,すぐれた文化の展開,人間的に魅力ある社会の安定的維持―これらを可能にする「社会的共用資本」とは何か.環境問題,農業,医療,教育といった各テーマに即して展開される,著者の思索の結晶.
内容説明
ゆたかな経済生活を営み、すぐれた文化を展開し、人間的に魅力ある社会を安定的に維持する―このことを可能にする社会的装置が「社会的共通資本」である。その考え方や役割を、経済学史のなかに位置づけ、農業、都市、医療、教育といった具体的テーマに即して明示する。混迷の現代を切り拓く展望を説く、著者の思索の結晶。
目次
序章 ゆたかな社会とは
第1章 社会的共通資本の考え方
第2章 農業と農村
第3章 都市を考える
第4章 学校教育を考える
第5章 社会的共通資本としての医療
第6章 社会的共通資本としての金融制度
第7章 地球環境
著者等紹介
宇沢弘文[ウザワヒロフミ]
1928年鳥取県に生まれる。1951年東京大学理学部数学科卒業。専攻は経済学。現在、日本学士院会員、東京大学名誉教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 4件/全4件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
なかしー
104
現代のSDGsやESGにも絡んでくる考え方の立案者の一人。 豊かな国とは?から始まり、それを実現するには「社会的共通資本」を軸にした制度主義によって「理想的な」経済体制を構築する事を目的とする。 社会的共通資本とは?①土地、大気、海洋などの自然環境②上下水道、公共的な交通機関、電力通信などの社会的インフラ③教育、医療、金融、司法、行政などを制度資本。管理・運営方法:それぞれの分野における職業的専門家によって、専門的知見にもとづき、職業的規律にしたがって行う。※政府による規定・基準やルール等に従わない2020/07/03
KAZOO
78
何度目かの再読ですが、いつも経済学と現実の接点をどのような観点から見るかを教えてくれる本です。理論ばかりではなくこのような考え方もあるのだ、ということをいつも教えてくれていて、経済政策、金融政策、環境政策、産業政策に参考になるヒントなどがあります。2015/05/30
ひろき@巨人の肩
73
Audiobookにて。経済学における新古典派と制度主義の比較から資本主義の理解が深まった。新古典派経済学は物理的な方法論から資本主義を捉えるため、近代工業による利潤追求が過大評価され、希少資本の枯渇や人間性・社会性の軽視といった現代社会の歪みを生む。その対策が制度主義。農業、都市、医療、教育、自然環境を社会的共通資本と定義し、近視眼的な個々人の利潤優先ではなく、持続的な全体社会の形成を念頭に、各々の共同体に最適な制度を構築すべきと論じる。理念に共感、でも実行が困難か。2019/05/08
saga
60
第1章は社会的共通資本の総論。経済学の講義のようでとても難解。第2章以降は、農業・都市・教育・医療・金融・地球環境と、個別具体的な各論で、こちらは判りやすかった。農業基本法が、個別農家と一工業事業所とを同列に位置づけていることへの問題提起をしているが、まったくそのとおり。「輝ける都市」の人間を無視した都市構想の問題も然り。地球環境での炭素税の考え方を発展させて、国連単位で炭素量に応じた基金への拠出+森林面積に応じた基金からの交付金という制度があれば、発展途上国の森林保護の動機づけにならないだろうか?2024/03/01
Sam
60
原理的に将来世代が参加できないことが市場主義の最大の欠陥だと思う。とすれば将来世代に引き継ぐべき「社会的共通資本」の重要性は絶対的なものであって、発行から20年が経過したいまも本書の価値は些かも変わらないはず。昔は宇沢先生は経済学に身を費やすことなく最初から「社会的共通資本」の構築に取り組んでいれば大きな成果に繋がったのではないかなどと思っていたが、経済学を極め市場主義が最も盛んな米国で過ごした経験があってはじめて「社会的共通資本」の考え方に至ったのであろうと考えを改めた。読み継がれ実践されるべき書物。2021/11/18