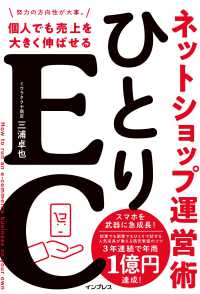出版社内容情報
逍遥の出世作として著名なこの書は,「小説神髄」の主旨を実証的に示すために書かれ写実主義小説の第一声として明治文壇に清新の気を注入した意義深い作品.当時の書生生活の雰囲気を如実に描写し,勧善懲悪という従来の小説手法から離れ,新機軸を出したもので,文学青年の多くがこの書に啓発された.明治18年刊.解説=柳田泉
内容説明
学生小町田粲爾と芸妓田の次とのロマンス、吉原の遊廓、牛鍋屋―明治10年代の東京の学生生活と社会風俗を描いた日本近代文学の先駆的作品。坪内逍遙(1859‐1935)は勧善懲悪を排して写実主義を提唱した文学理論書『小説神髄』とその具体化としての本書を著し、明治新文学に多大な影響を与えた。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
優希
92
面白かったです。掛詞が巧みに使われており、独特のテンポを感じました。明治10年代の東京を舞台にした学生生活と社会風俗が笑えます。散歩し、酒を飲み、語りあう。その話題が金と女というのは何と言うべきか、ですね。昔も今も学生の根本的な部分は変わってないんだなと思いました。2016/08/28
夜間飛行
82
人物より運命に重きを置いている話のようだ。それにしても田の次という芸者さん、まだ17、8なのにしっかりしている。面白いのは書生の生態で、門限ををごまかす算段がつくと牛鍋屋や寄席に立ち寄ったり、《人素三分化素七分の白首連の巣窟》とある遊里で白首の女どもに拉致されたあげく、二十銭払って解放される。序文で逍遙は勧善懲悪を旨とするものではないことを繰り返し述べている。読者はここから好きな教訓なり娯楽なりを、自由に引き出してくれればそれでいいのだと。宣長や逍遙の小説論は今でも参考になるから、教科書に載せたらどうか。2018/07/04
みつ
26
名のみは昔から知っていた本作。明治期前半の書物をいろいろ読む中で遂に手を出す。多くの書生が登場し、芸妓と懇意になるは借金はこしらえるは、政党に入党したり大学を退学しても翻訳で食いつなぐなど、自由気儘な生活ぶりが伺える。ペダントリーが随所に顔を出す会話描写であるが、あまり勉学に勤しんでいるように見えないのはなぜ? 女性との関係はほぼ芸妓に限られるというのは、明治も後半の小説とは相当異なる印象。政府高官の妻も元芸妓であった時代でもあり(p239の会話参照)、「芸妓をワイフにするは身を立てるの障害」➡️2023/11/15
ステビア
22
日本近代小説の嚆矢と言われる作品。それはさておいても面白く読める本だ。2016/08/17
藤月はな(灯れ松明の火)
20
「夢魔は蠢く」に収録されている役小角の伝奇でも同じく、「小説神髄」でお堅いイメージが強いですが、意外と読みやすく、面白い坪内逍遥氏の文体に圧倒されました。まずは借金対戦の名前が「臍繰朝泰(へそくりちょうだい)」などが使われている所やわざと英語で気取っているのが可笑しかったです。多分、当時はこの作品を読んだ年配の方が「最近の若者(書生)はなっとらん!!」と噴飯していたんじゃないかしら(笑)文学研究会の文学少年の先輩にこの本を薦めたところ、文体を見て「歌舞伎みたいに韻を踏んでいる」とおっしゃりました。2011/09/30
-
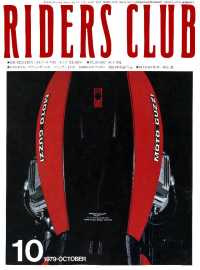
- 電子書籍
- RIDERS CLUB No.16 1…