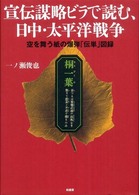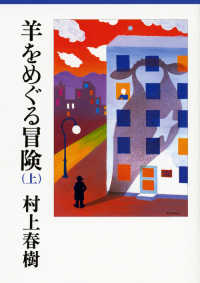内容説明
咸臨丸による渡米、不偏不党の新聞『時事新報』創刊、そして慶應義塾の創設と教育改革――。開国に伴う体制一新の時代、勝海舟、北里柴三郎、川上音二郎ら傑物との交流と葛藤の中で、国民たちの独立自尊を促し、近代日本の礎を築いた福澤諭吉の生涯。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
starbro
157
上下巻、700頁強、完読しました。激動の時代で、福沢諭吉という素材ならもっと面白くなりそうだったんですが、福沢諭吉の自伝のリライト小説のせいか、あまり面白くありませんでした。慶應大学OBにもオススメしません。 著者は、これが最後?の小説のようですが、著者らしい荒唐無稽な小説で終わって欲しい気がします。 https://www.hayakawa-online.co.jp/shopdetail/000000015609/2024/04/11
KAZOO
101
福沢節というよりも荒俣節が聞こえてきそうな感じの話ぶりです。下巻では弟子たちとのやり取りが主な感じとなっています。小泉新吉とのやり取り、あるいは北里柴三郎へのサポートなどが主体でわたしの知らないことがかなり多くありました。最後のエピローグでは「死から覚めて視た未来」ということで昭和五十二年に遺体が掘り出されたことが書かれています。「福翁自伝」を読みなおそうかと思います。2024/02/25
ばんだねいっぺい
27
どうも、ドイツモデルにしたことや、科挙制度の輸入のような官学や、極めつけは、教育勅語。この流れには、キナ臭いものを感じてしまった。先生の夢がこの日本をまだまだ支えてくれることを祈るのみ。2024/12/29
ちゃま坊
19
新札に渋沢栄一の登場で福沢諭吉を再考。明治期の若者が目指した二つの道の対比。国立学校を出て役人や軍人になる道。これは「坂の上の雲」。もうひとつは私立学校を出て自由な職を見つける道。これは緒方洪庵「適塾」のスタイル。本来翻訳と蘭方医学の塾から、福沢や大村益次郎など多才な人材が輩出された。慶應義塾は今でも私学の雄。アラマタ先生のような多才な作家が出るのもうなずける。2024/09/16
maimai
11
うむむ。上巻は調子よかったんだけどなあ。福沢諭吉について書くときにこういう叙述の形式をとった意図はわかるし、というかなるほどなぁとも思ったのだが、そしてそれは博覧強記の著者ならではの発想だとも思うのだが、それは碩学・荒俣宏の素晴らしいアイディアではあったとしても、それを物語る小説家・荒俣宏の手には余ったんではないかなぁ。『帝都物語』を読んだときにも感じた、「この話はもっと面白いはずなのに、読んでいてもっと血沸き肉躍る心地がしないのはなぜだろう?」という感覚を思い出した。2024/01/23
-

- 電子書籍
- 少女たちのエロ漂流記【全年齢版】(4)…
-

- 電子書籍
- 週刊ベースボール 2025年 1/20号