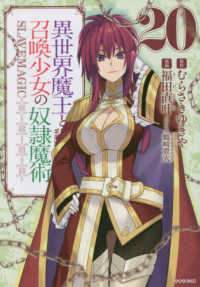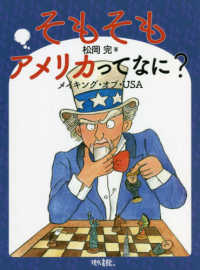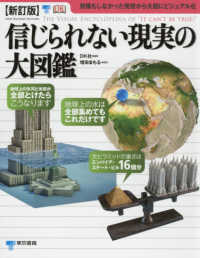内容説明
科学は戦争をやめさせることができるのか? 生物学者が迫る人間行動の謎!
人間は戦争や暴力のような「最悪の行動」と、協力や利他といった「最善の行動」のどちらも選択しうる。その善悪を分けるものは何か? 下巻では、〈我々〉と〈彼ら〉を区別するという態度や、集団の中の序列が形成される仕組みについて、霊長類学、社会心理学、文化人類学から行動経済学といった学問分野を横断して考える。集団どうしの間で起こる暴力、戦争という「最悪の行動」を避けるために科学にできることを探求する著者はどんな希望にたどり着くのか?
【内容】
第11章 〈我々〉対〈彼ら〉(霊長類学、社会心理学)
第12章 階層構造、服従、抵抗(社会心理学、内分泌学)
第13章 道徳性と正しい行動(道徳哲学、行動経済学)
第14章 人の痛みを感じ、人の痛みを理解し、人の痛みを和らげる(認知心理学、動物行動学)
第15章 象徴としての殺人(神経生物学、表彰文化論)
第16章 生物学、刑事司法制度、そして(ああ、もちろん)自由意志(生物学、社会心理学)
第17章 戦争と平和(心理学、霊長類学)
エピローグ
付録1 神経科学初級講座
付録2 内分泌学の基本
付録3 タンパク質の基礎