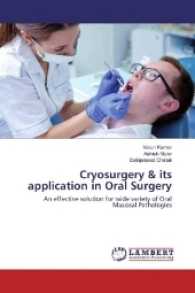内容説明
新聞や雑誌、小説、落語、童話、ライトノベル、ゲーム……怪異は多様な形式に合わせて姿を変えて人々に受容され、ときに社会に大きなインパクトを与えてきた。怪異はどのように書き留められ、表現され、創作されてきたのだろうか。
創作活動にとっての怪異を語る小説家・峰守ひろかずへのインタビューを筆頭に、円朝の怪談噺、劇場空間と怪異、超常能力表象、子どもと怪異、怪談実話、『刀剣乱舞』など、バラエティー豊かな怪異の物語を読み解き、怪異を魅せる/怪異に魅せられる心性を問う。
目次
はじめに 一柳廣孝
第1章 怪異を書く:峰守ひろかずインタビュー 聞き手:飯倉義之/一柳廣孝
第1部 怪異を物語る――怪異を伝えるために試みられたこと
第2章 挿絵が語る怪談噺――『真景累ヶ淵』と『怪談乳房榎』の場合 横山泰子
1 『真景累ヶ淵』の場合
2 『怪談乳房榎』の場合
第3章 豆男物の浮世草子――浅草や業平伝説との関係など 佐伯孝弘
1 豆男物の定義と範囲
2 浅草や業平伝説との関係
3 小説史のなかの位置づけ
第4章 劇場空間と怪異――泉鏡花「陽炎座」が描く観劇体験 鈴木 彩
1 子供芝居の幕の裏には……
2 拙い芝居を観ることの意味
3 虚構が、虚構であることをやめるとき
第5章 超常能力と大正中期探偵小説 浜田雄介
1 読唇術探偵の誕生
2 シンパシーと探偵の自壊
3 解ける謎と解けない怪異
第2部 怪異で物語る――怪異を通じて語りうること
第6章 子どもと怪異――松谷みよ子『死の国からのバトン』を考える 三浦正雄/馬見塚昭久
1 ムーブメントの交差点
2 怪異の仕組み
第7章 船幽霊の声/幽霊船の沈黙――〈海異〉の近代文学史 乾 英治郎
1 近代の〈海異〉――明治期を中心に
2 関東大震災と〈海異〉
3 昭和期の〈海異〉
第8章 往生際の悪い死体――執着譚と蘇生譚の境界 近藤瑞木
1 実録的「蘇り譚」
2 「是よみがへるにはあらざる事」
3 臨終行儀書の姿勢
4 蘇生者の殺害――『伽婢子』と『雪窓夜話』
5 西鶴の「ためしもなきよみがへり」
第9章 枕のなかの世界――『唐代伝奇』「枕中記」の日本受容 笹生美貴子
1 古代日中の「枕」にまつわる作品――魂との関連に注目して
2 枕の穴――壺中天・太湖石が織りなす世界観との関連性
3 「枕中記」の日本受容
第3部 怪異は物語る――怪異に読者が期待すること
第10章 インディアン・ロープ・マジック幻想――幸田露伴から手塚治虫まで 橋本順光
1 インディアン・ロープ・マジックの発見と幻滅
2 物語でのロープ・マジックの再生と転用
第11章 「情報化」される〈怪異〉――『刀剣乱舞』からみる現代版「付喪神」の表象 上島真弓子
1 『刀剣乱舞』――現代版付喪神の登場
2 「三日月宗近」の擬人化
3 祟りからロマンへ――恐怖からの脱却
第12章 怪談の文法を求めて――怪談実話/実話怪談の民話的構造の分析 飯倉義之
1 怪談実話/実話怪談とは「何か」
2 怪談の「実話らしさ」とは何か
3 怪談実話の「文法」を読み解く
4 怪談実話を「文法」で読み解く
おわりに――シリーズとしては「つなぎに」 飯倉義之
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
へくとぱすかる
qoop
mittsko
集積屋
-

- 電子書籍
- 大きな文字でよみやすい! 電子レンジで…