- ホーム
- > 電子書籍
- > ビジネス・経営・経済
内容説明
※本書はリフロー型の電子書籍です
【ChatGPTはブームではない。テクニウムがもたらすゲームチェンジに備えよ!】
2023年は生成AIに関するニュースが毎日のように報じられていて、技術のトレンドも最新の状況も猫の目のようにくるくると変わっています。しかし、じっくり腰を据えて見渡してみれば、いま起きていること、そしてこれから起きることは、「検索」から「生成」という大きなパラダイムシフトであると捉えることができるのです。生成AIはブームではありません。新しい時代の幕開けなのです。本書では「検索から生成へ」といたるパラダイムシフトはなぜ、どのようにして起きたのかを歴史的背景から紐解き、これから起きることはなにかを考えていきます。
〈目次〉
序 ~まえがきにかえて~
プロローグ 検索の時代
検索以前の時代とインターネットの誕生/人力によるディレクトリ検索/自動で探索するロボット型探索/「そんなに検索精度が高いと儲からない」/KPIは顧客滞在時 …ほか
第1章 生成AIとはなにか?
コンピュータとAIは真逆の存在/説明なしで学ぶ人工ニューラルネットワーク/巨大化することで性能を飛躍的に向上させた生成AI/生成AIの性能を決定づけるデータとバイアス …ほか
第2章 テクニウムがもたらす未来~知恵を合わせる能力~
AIが急速に進歩した理由/Microsoftはなぜ大学生に負けたのか?/ファミコンから始まったゲーム機戦争/PCとMac、GPUの共進化/WebサービスとWeb2.0/強化学習×大規模言語モデルがChatGPT …ほか
第3章 民主化された生成AIが世界を変える
大規模言語モデルが民主化されるとなにが起きるのか/生成AIの法的な問題/倫理的な問題/データ中心主義(データセントリック)/表現手段としてのAI/プログラムを書くAI …ほか
第4章 生成AIでビジネスはどう変わるのか
生成AIでプロジェクトを管理するコミュニケーションと生成A経営者と管理職を助ける生成AI/中小起業こそ生成AI導入のメリットがある/生成AIで変わる人事/生成AI時代の組織とは …ほか
第5章 生成AIの可能性
コミュニケーションと生成AI/エンターテインメントと生成AI/プランニングと生成AI/仕事と生成AI/新しい働き方と生成AI/教育と生成AI/高齢化社会と生成AI
おわりに 「永続する未来へ」
〈本書の内容〉
生成AIでビジネスはどう変わるのかを事例とともに考察するほか、「生成の時代」をヒトはどう生きるべきかまでを人工知能研究の第一人者が解明!
〈著者プロフィール〉
清水 亮(しみず・りょう)
新潟県長岡市生まれ。AIスペシャリスト。プログラマーおよび上級エンジニア経験を経て、1998年に株式会社ドワンゴに参画。2003年に独立し、以来20年で12社の設立に関わるシリアルアントレプレナー。2005年、IPA(情報処理推進機構)より「天才プログラマー/スーパークリエータ」として認定。2017年、2018年 内閣府知的財産戦略本部「新たな情報財検討委員会」委員。2018年から2023年 東京大学客員研究員。2019年、2020年 一般社団法人未踏とNEDOによる「AIフロンティアプログラム」メンター。著書に『よくわかる人工知能』(KADOKAWA)、『はじめての深層学習(ディープランニング)プログラミング』(技術評論社)、『最速の仕事術はプログラマーが知っている』(クロスメディア・パブリッシング)、『プログラミングバカ一代』(共著、晶文社)がある。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
よっち
ま
チャー
nbhd
owlsoul
-

- 電子書籍
- リターンサバイバル【タテヨミ】第58話…
-

- 電子書籍
- 悪役令嬢に転生したら敵国密偵に求婚され…
-
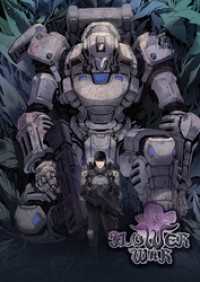
- 電子書籍
- 12話【タテヨミ】
-
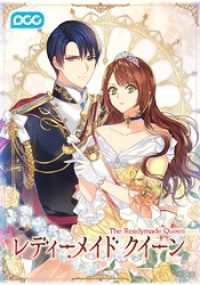
- 電子書籍
- 29話【タテヨミ】
-
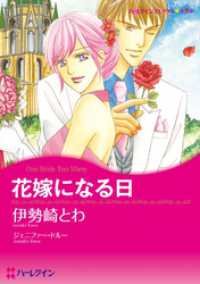
- 電子書籍
- 花嫁になる日【分冊】 7巻 ハーレクイ…




