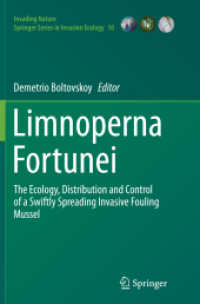- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
明治維新による誕生から今日までの約150年間、破壊と再生を繰り返しダイナミックに発展してきた帝都/首都東京。巨大都市はいかに形作られ、人々はどのように暮らしてきたのか? 関東大震災や太平洋戦争からの復興、高度成長とオリンピック、バブル経済とその崩壊、住まいとインフラ、自治と首都機能、工業化と脱工業化、繁華街と娯楽、高層化と臨海副都心開発――今や世界的都市となった東京を様々な角度から見つめ、読み解き、その歴史を一望する。まったく新しい東京史。
目次
プロローグ/今の都心の姿から考える/本書の視点/本書で取り上げること/第1章 破壊と復興が築いた都市/戊辰戦争と近代の始まり/最初の本格的な都市計画/都市計画が直面する社会/災害の克服を目指す──荒川放水路の整備/関東大震災と復興/公園は誰のためか?/都市に葬る/緑地はいかにつくられたか?/空襲の本格化のなかで/戦火をくぐり抜けた街並みを求めて/うまくいかなかった戦後の復興計画/東京オリンピックと都市改造/埋立地からできた都市/埋立地の多様な使われ方/都市の再生か、経済の再生か?/第2章 帝都・首都圏とインフラの拡大/「帝都」と「首都」の来歴/帝都交通網の拡大/暴動の標的となった路面電車/多摩の近代/市域拡張とは何か?/東京のなかの島嶼/首都圏の誕生/戦後の交通網拡大と終わる都電の役割/首都圏の諸県と東京のつながり/首都圏の未来/第3章 近代都市を生きる民衆/自由放任時代の都市/「スラム」という空間/都市民衆騒擾とは何だったのか?/男性の心情から暴動を説明する/社会都市の形成/公設市場・食堂・職業紹介所/「行き倒れ」る人々/朝鮮人と東京/関東大震災と朝鮮人/昭和初期の貧困を生きる/貧困のどん底/子供の労働のありよう/『綴方教室』の反響/敗戦後の戦災孤児/住宅不足と団地・木賃アパート/集団就職と若者の労働環境/開発を支えた労働者たち/第4章 自治と政治/東京府と東京市/東京都の誕生は戦時下だった/汚職が多発した東京市会/選挙粛正の掛け声のなかで/日比谷公会堂と東京市政調査会/都市の「美」は排除を伴うのか?/敗戦から高度経済成長期の都政/革新都政の誕生/保守による都政の奪還/世界との都市間競争/第5章 工業化と脱工業化のなかで/近代東京と工業/都市化のなかの農業と屎尿/戦後の屎尿処理問題/戦前の労働問題/横浜と東京の都市間競争/三多摩での都市間競争/高度経済成長と工業/脱工業化の時代のなかで/スマートシティとは?/第6章 繁華街・娯楽と都市社会/近現代東京と繁華街/近代の大イヴェント/「花街」とはどういう場所か?/ツーリズムと戦争/帝都の復興を祝う/オリンピック・万博と紀元二千六百年/紀元二千六百年関連行事と社会への影響/ヤミ市と戦後の駅前繁華街/月島という街/第7章 高いところ低いところ/山の手と下町/川と生活/近代における高い場所/関東大震災前からあった丸ビル/さらに高いところを求めて/アーバン・ルネサンスからバブルへ/バブル崩壊から都市再生の現在へ/都市再生は未来に何を残すか?/エピローグ 東京を通してみた近現代/近代の工業化と貧困への対応/帝都の復興とさらなる破壊/敗戦から高度経済成長期の社会と政治/ポスト高度経済成長の都市空間/東京史に残された課題/あとがき/東京史関連年表/参考文献
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
bapaksejahtera
spike
あきひと
安土留之
かわくん
-

- 電子書籍
- 週刊SPA! 2025/01/14・2…
-
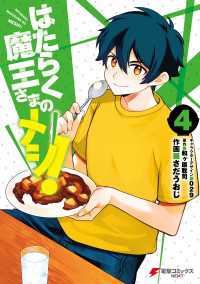
- 電子書籍
- はたらく魔王さまのメシ!4 電撃コミッ…
-
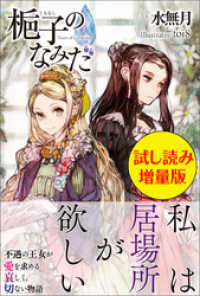
- 電子書籍
- 梔子のなみだ〈試し読み増量版〉 PAS…
-

- 電子書籍
- 執事に学ぶ 極上の人脈(きずな出版) …