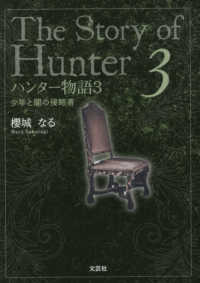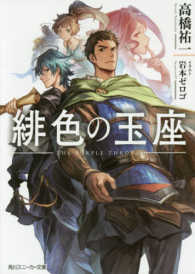内容説明
人間は社会に属することで一つの集団としての属性を強める一方で、集団外の人を違うものとみなして敵視することがある。他の生物と比較して、なぜ人間は小さな違いにこだわり、仲間と敵を区別するのか。人間社会の成り立ちを生物学的な見地から解き明かす。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Koichiro Minematsu
64
まだ上巻ですが、マジで面白い! 最初は分かりませんでしたが、表紙に何故アリが人といるのか、読み進めると納得です。タイトルからして感情論の部分を読みたかったのですが、そうではありません。社会性のある学問です。自分なりの現段階での憎しみあう理由は、アイデンティティ・バイアス・匿名性です。更なる下巻に期待!2022/01/06
りょうみや
22
蟻の研究者が書いた人間の社会性についての内容。進化心理学や社会心理学に基づいた同内容の本は多いが、本書は著者専門の蟻を含め、様々な群れをつくる動物達と対比することによって、人間の群れの特徴を浮かび上がらせている。人間が街中で見知らぬ人たちと普通に通り過ぎているのは、生物の中では特異な能力と言う。人間は共通の「しるし」で同族を認知しているのだが、それから人間のアイデンティティの根本のところまで話を進めていく。上・下合わせて一気に読む。2020/12/16
テツ
14
群れるのはそこに属する個々人の生存競争を有利にするため。そして群れ以外の他者(たち)は生存競争におけるライバルである。更に人間は群れの利益のためだけに存在することはできない。異なる価値観、思想信条、群れの形に感じる好き嫌い。そうした小さな差異を群れを形成する膨大な数の個人同士が群れの中でぶつけ合い反目しあう。そりゃみんなで仲良く手を繋ぎ助け合おうなんていうお題目はそうした在り方の前では虚しく響くだけだよなあ。何とかして人の群れを一段階上のステージに進めることはできないものか。下巻も楽しみです。2022/09/09
flat
9
生物学的な観点から人間の社会性について書いてある。生きるにあたって群れという概念が存在する。そして群れの外は生存競争における競争相手である。従って排除機能が働く。皆で仲良く手を繋いでというのが如何に難しいことなのかというのが分かる。それはおそらく生物の持つ本能への挑戦なのだ。2021/04/04
くらーく
3
どうかな。著者の経歴と社会学とか心理学とかの結びつきが何とも。確かに蟻と人類と、こうやって対比すれば似ているけど、違いが圧倒的すぎない? 憎しみ合う理由が群れだとすれば、これからの人類はますます希望が無くなるなあ。 まあ、下巻をじっくり読みますわ。2022/03/04