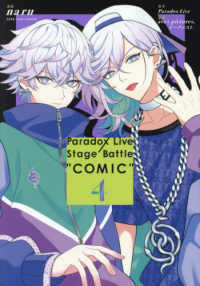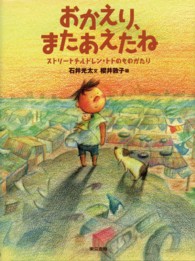- ホーム
- > 電子書籍
- > ビジネス・経営・経済
内容説明
雇用消滅と社会混乱を、日本はどう生き延びるか。
AIが世界中の富と雇用と税収を米中にかき集める一方、両国内ではAI独占企業が誕生し、貧富の格差が激化する。
AI技術を獲得できなかった他国は、隷属の道を歩むーー。
中国IT業界の先駆者が、来たるべき新しい世界秩序を描く。
目次
はじめに
1 中国のスプートニク的瞬間
2 模倣者たちの大競争
3 中国のインターネット並行宇宙
4 中国対アメリカ
5 AIの4つの波
6 ユートピアとディストピアとAI危機の本質
7 AIと人間性--癌の教え
8 人間とAIの共生に向けて
9 AIの未来を描く
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Ujiro21
4
Amazonリストより。TikTok前2020年の本。カイフ・リー氏のAI2040が面白く期待値高めで読む。偽ミッキーがパクりと嘲笑されていた時に、苛烈な生存競争を生き抜いたテック起業家のしたたかな野心と著者がGoogle chinaで米国本社のグローバル対応しか取らない姿勢に思う事など文化的な違いが面白かった。後半は著者の半生、台湾生まれ米国で学びAppleでの音声AI研究者としての成功とベンチャーキャピタルに至る経緯、説得力の強さよ。リンパ腫に侵され、技術力を人重視の価値とした辺り尊敬。産業革命の時か2023/04/26
水判土カスミ
4
AIやIT技術の未来予想や現状に関する本ですが、日米が中心と書かれている他の本に対してこの本は中国の状況や歴史がメインに書かれており、中国の方が進んでいるのではないか、と思うところもありました。2020/06/27
yutanpo
3
おもしろかった。どうしても西側からの情報に頼ってしまうけど、東側から見ると全く景色が違っておもしろい。2022/04/24
四ツ谷
3
AI企業について調べていると著者の名前をよく拝見したので手に取った。中国がなぜパクることを辞めないか気になる人にはよい資料となるだろう。中国は知財を電気の発見のように捉えている。電気を使うことに特許料を支払うのか、そうではなく電気を使うことに如何に恩恵を得るかというように。産業革命時に機織師など多くの職人が工場の機械を破壊する「ラッダイト運動」を起こした。しかし、実際は労働市場が拡大し、失業者たちを市場が飲み込んだ。イノベーション楽観論があり、それに対する反対論が本書にまとめられている(ヽ´ω`)2022/01/16
アルミの鉄鍋
3
★3 米中のAIの実力の差。どちらが派遣を取るのか。パクリと言われた中国も最早、1人で動けるほどの戦略を持ち国の中を変えようとしている。米国はそんな中国に制裁でコントロールしようとしており、そんな米国をヨーロッパはルールでコントロールしようとしている。どこが覇権をとっても良いので利益ばかり見ずに人間にとって何が正しいのかを全員で考えて正しい方向に進んでほしいなと思う。2020/09/08
-

- 和書
- 玉川学校劇集 〈5〉