- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
いま、中世史に新たな光が当てられている。東アジアのなかで日本列島を捉えなおす視点の導入や、文献史料以外の多様な史料も視野に入れた研究の進展などがその一例である。戦国期以外の中世への一般の関心も高まっている。そこで、最新の調査・研究の成果や動向を一般読者にわかりやすく伝えるべく、先端研究者の知見を結集。時代の推移に沿った構成をとりつつも、平板な歴史叙述ではなく、政治・経済・外交・社会・文化など15の重要ポイントを押さえる形で中世史を俯瞰する。
目次
1 中世史総論 高橋典幸/2 院政期の政治と社会 佐藤雄基/3 日宋・日元貿易の展開 榎本渉/4 武家政権の展開 西田友広/5 鎌倉仏教と蒙古襲来 大塚紀弘/6 荘園村落と武士 小瀬玄士/7 朝廷の政治と文化 遠藤珠紀/8 南北朝動乱期の社会 高橋典幸/9 室町文化と宗教 川本慎自/10 中世経済を俯瞰する 中島圭一/11 室町幕府と明・朝鮮 岡本真/12 室町将軍と天皇・上皇 三枝暁子/13 戦国の動乱と一揆 呉座勇一/14 戦国大名の徳政 阿部浩一/15 中世から近世へ 五味文彦
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ホークス
34
2019年刊。面白かった点。①対宋・元貿易は、変化する双方の国情に伴って公認と禁止を繰り返した。②律令制度は早くから崩れた。例えば宮中の食事に関する役所は内蔵寮、大膳織、内膳司、造酒司だが、特定の家(山科家等)の請負い、兼職の増加により職員は減った。③徴税を担う国衙が衰え、貴族や寺院は自ら徴税に乗り出し、これが荘園制へと繋がる。国衙の職人が自営化。④貢納物の輸送は平安末から一部が銭貨に、鎌倉期には銭貨から手形に置き換わり金融業が勃興。室町期に地域権力が強くなると地消化で輸送が細り、京都や鎌倉の金融業は衰退2025/01/13
浅香山三郎
17
ちくま新書でシリーズ化されてゐる『○○史講義』の1冊。比較的短く、しかしそれなりに質を保つてといふ水準があるのだらうが、皆さんうまい。とくに興味深つたのは、「荘園村落と武士」、「中世経済を俯瞰する」、「室町幕府と明・朝鮮」あたり。2019/03/18
nagoyan
15
優。日本中世史を、新書という手軽な形ではありながら、政治史、経済史、社会史、文化史という広い範囲にわたり、その研究の現在を紹介したもの。入門書として読まれることを意識して、各章末に参考文献が示されているのも親切。2022/02/12
niwanoagata
15
なかなか面白かった。主に研究史の整理だが、普段読まないような内容も多く勉強になった。個人的には前半の方が面白かった様に感じた。内容が幅広いので批評はしない。2020/07/08
かんがく
15
明治、古代に続いて読了。このシリーズは研究者がそれぞれの専門について最新の研究状況を教えてくれるので良い。中世については今年度たくさん読んだので、ちょうど良い復習になった。天皇、貴族、武士、寺社、庶民とアクターは多数いるが、イエと分権がキーワードだろうか。宗教、経済、外交の章が特に興味深い。2019/02/17
-

- 電子書籍
- ブレッチェン~相対的貧困の中で~(分冊…
-

- 電子書籍
- 阿修羅ゲート67
-

- 電子書籍
- 魔物を狩るなと言われた最強ハンター、料…
-
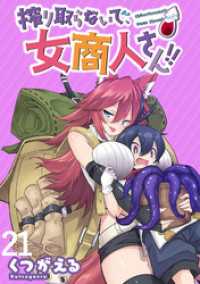
- 電子書籍
- 搾り取らないで、女商人さん!! WEB…
-
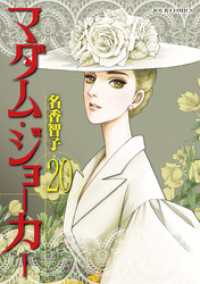
- 電子書籍
- マダム・ジョーカー 20巻 ジュールコ…




