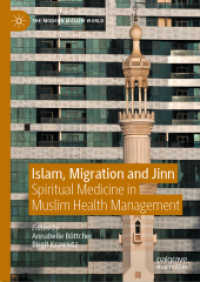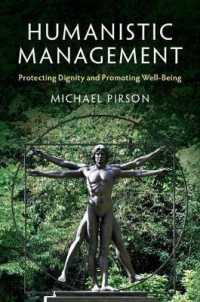内容説明
江戸時代の百姓たちにとって、食料、田畑の肥料、燃料、建材など山から得られる資源の確保は、死活問題だった。 山は近隣の村々で共同利用されることが多かったが、山のどこまでが自村の領域かをめぐって村々はしばしば対立し、領主や幕府にしきりに訴訟を起こした。 時を経て明治を迎えると、政府の近代化政策により村々は村境画定を迫られ、山争いはいっそう過熱してゆく。 山をめぐる熾烈な争いと相互協力への努力を、当事者の肉声をふまえて克明に描く。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
樋口佳之
42
百姓がタイトルだけど、本当の主役は百姓の作った村なのではないかと感じた。いずれにせよ、自らの労働条件確保に粘り強く訴訟に取り組む姿は、唯々諾々と支配されるだけの百姓像とは無縁。訴訟記録が当地の寺子屋の教本として利用されたとかもすごいなあ。2020/08/24
アナクマ
32
複数の事例を丹念に追う。例えば山形県山口村と田麦野村。両者とも所有権より利用権を重視。決着のポイントは、近代法制度の実行と、利用の必然性にあると見た。争いつつも、山林の重要さは互いに共有できていたのだ。◉顛末記に曰く「森林の無限の生産力への信頼。それを利用しての、町と町民の福利増進への期待」。その素朴な楽天性には複雑な思い。◉山林から糧を得る必要がなくなり「どうでもいいもの」となる事が最も憂慮すべきこと。ヒトの生息域の何倍も広く存在するのに、山はいつも忘れ去られがち。2019/03/01
to boy
25
百姓って畑や田んぼで働いているだけではなく山に入って薪炭を取り草を刈って肥料にしたりと畑仕事以外にも活動していたことにあらためて気付きました。また、武士との関係も対立するだけでなく領地を守るために共同して訴訟に当たったりしたことも驚き。百姓にとって山は所有よりも使用する権利の保持が死活問題であったこともなるほどでした。実際の百姓たちの生活に少しだけ触れたような気がします。2017/12/05
ヤヨネッタ
5
第三章の名主・伊藤義左衛門さんを主人公にした江戸での裁判の部分が人間臭くて特に面白かった。入牢する可能性を考えて傷に塗る特効薬を入手して地元にも送ったり、百姓一揆を題材にした歌舞伎に感動しまくりながらも、身につまされる内容過ぎて辛くて最後まで見られなかったり(感想文と一緒に物語の冊子を10冊も地元に送った)など。江戸から明治まで、百姓も武士も役人もしたたかにしぶとく証拠を揃えて裁判を闘ってきた。落としどころを見つけた後、対立してた自治体がそれぞれ結果を「勝訴」としてた事実も味わい深い。2019/10/08
コーリー
4
江戸・明治を主要な対象時期として、森林・山野をめぐる人々の営みについて書かれた本。本書では様々な事例が紹介されており、中には300年にわたって続いた案件もあって、当時の人々にとって林野が生産と生活に不可欠の土地であったことが実感できた。また中世までの実力行使が禁止され、訴訟によって自村の権益を守ろうと奮闘した当時の百姓たちの姿や、訴訟の中での「越訴」や「公事宿」,共通の利害に立って協力しあった村人と代官の関りなどについて知ることができ、興味深かった。様々な事例を通じて当時の人々の思いを感じることができた。2019/05/20