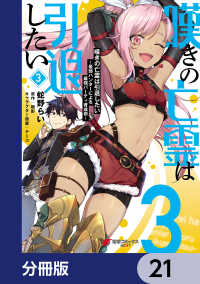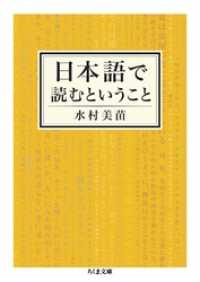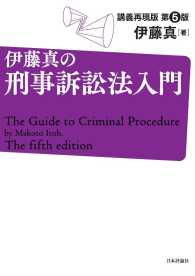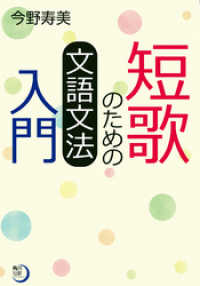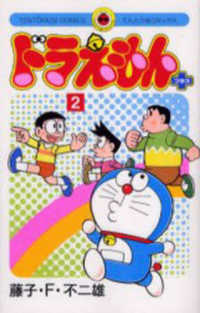内容説明
フーコーの権力論は1970年代半ば、『監視と処罰』と『知への意志』で頂点に達する。だが『狂気の歴史』に始まるラディカルな思索は、権力と抵抗の二元論として受容された。しかしこの時期、フーコーの思索には新たな展開が生じていた。〈統治〉概念の導入を契機に、権力論が再構成され、倫理、自由、主体化、パレーシアの概念を軸に、独自の主体論が立ち上がる。そして〈統治〉する〈主体〉が姿を現す。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
koke
11
後期フーコーの著書だけでなく、お高い講義録も読み込まなければ分からない「統治」。その意義を一冊で概観できる。いい買い物をした。後期フーコーは「倫理」や「美学」を語るが、では「政治」はどうなったのか、「権力の外部はない」とした上でそれらはどう共存するのかが分かりづらい。それらを取りまとめる大きな枠組みが実は統治だった。つまり自己と他者の、またミクロとマクロの、導き、導かれ、対抗導きする運動だ。2022/11/09
Mealla0v0
5
後期フーコー(権力論~統治論の時期)の思想に関して、日本語で読める文献として重要な著作。フーコーの思想を権力/抵抗の二元論から統治一元論への移行・深化という形で捉えており、フーコーのポジティヴな側面を描き出している。2020/06/09
zk
1
途中までそれほど新味が感じられないと思っていたら終章が大変に示唆的で、おそらく何度か読み返すことになる予感がしています(というか終章のためにきっちり議論を積み上げていたということでしょうか、なんか反省…)。2023/08/23
ゴリラ爺
1
本書では『安全・領土・人口』で使用されてすぐ棄却された「対抗導き」が鍵語になるが、例えば『主体の解釈学』では、導きを表す言葉も教導(ペダゴジー)や師導(メルクリーズ)など意味に傾斜をつけて細分化し深化して語られているので、それを単に「導き-対抗導き」という図式に落とし込むキャッチーさに乗り切れなかった。統治一元論として見通しをよくするためだったのだろうが、突っ込みどころが多く、ある概念を説明するために抜かしてはならないだろうという文脈が簡単に省略されていてどうなんだろうと疑問に思う箇所が多かった。2023/03/07
NO MORE MR.NICE GUY
1
後期フーコーの「統治」概念において、権力、すなわち他者による自己の統治、と、抵抗、すなわち自己による自己の統治が一元論的に共存しうることを論じている2014/05/29