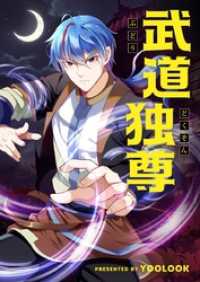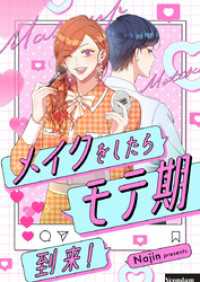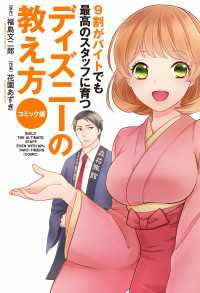内容説明
『日本語が亡びるとき』はなぜ書かれることになったのか? そんな関心と興味におのずから応える1990年代から2000年代の間に書きつづられたエッセイ&批評文集。文庫版あとがきを加えて待望の文庫化。12歳でのニューヨークへの移住、パリでの留学生活、子供時代からの読書体験、加藤周一や辻邦生ら先達への想い――。英語ばかりの世界で過ごした著者にとって“日本語”で“読む”とはどんなことなのか。
目次
Ⅰ 本を読む日々
「善意」と「善行」
パンよりも必要なもの──文学全集の愉しみ
美しく生きる──中勘助『銀の匙』
ほとばしる凝縮された思い出──吉川英治『忘れ残りの記』
私が好きな『細雪』
半歩遅れの読書術
たくさんの着物に彩られ綴る女性の半生──幸田文『きもの』
「大作家」と「女流作家」
「よい子」とのお別れ──『或る女』との出会い
わたしはそれでもこの日本を愛せるか──キク・ヤマタ『マサコ
麗しき夫人』
女は何をのぞんでいるのか──ジェーン・オースティン『高慢と偏見』
Claire Tomalin『Jane Austen(A Life)』
私の名作玉手箱──エミリー・ブロンテ『嵐が丘』
布の効用──バーネット『小公女』
言語の本質と「みなしごもの」
私の「海外の長編小説ベスト10」
ガートルード・スタインを翻訳するということ──『地球はまるい』
昔こんな本が在った──松島トモ子『ニューヨークひとりぼっち』
何をやるのも一緒──辻佐保子『「たえず書く人」辻邦生と暮らして』
「死んだ人」への思いの深さ──関川夏央『豪雨の前兆』
Ⅱ 深まる記憶
数学の天才
美姉妹
「エリートサラリーマン」
今ごろ、「寅さん」
子供の未来
街物語パリ
至福の瞬間とき──ジョン・トラヴォルタ
双子の家
翻訳物読まぬ米国人──NYの国際文学祭に招かれたけど……
日本の「発見」
人間の規範
あこがれを知る人
第十一夜
漱石の脳
使える漢字
中国から来たもの
私が知っている漢詩
ヨーガン・レール氏の洋服
ラクソ・ランプ
Ⅲ 私の本、母の本
『續明暗』のあとに
『續明暗』──私なりの説明
自作再訪──『續明暗』
『私小説from left to right』について
灼熱のインドと雪夜のアメリカ
「野間文芸新人賞」受賞スピーチ
祖母と母と私
『本格小説』を書き終えて
『本格小説』と軽井沢
「読売文学賞」受賞スピーチ
韓国の読者のみなさまへ
恩着せがましい気持……
女だてらに
Ⅳ 人と仕事のめぐりあわせ
作家を知るということ
「個」の死と、「種」の絶滅──加藤周一を悼んで
辻邦生さんの「偲ぶ会」スピーチ
最後の最後の手紙
あとがき
文庫版あとがき
初出一覧
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ユ-スケ
トビケ
Yasuyuki Kobayashi
Hitoshi T
N