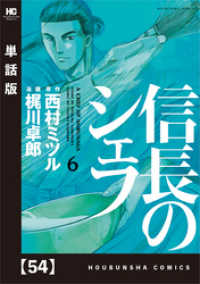内容説明
朝令暮改の文科省に翻弄され、会議と書類の山に埋もれながらも研究、講義に勤しむ工学部平教授。安給料で身体を酷使する「女工哀史」さながらの毎日。累々たる屍を踏み越えつつ頂上を目指す大学出世スゴロク。そして技術立国日本の屋台骨を支える「納期厳守」「頼まれたことは断らない」等エンジニア七つの鉄則。理系裏話がユーモアたっぷりに語られる、前代未聞の工学部実録秘話。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
382
冒頭にも言及されているが、本書はかつてベストセラーになった筒井康隆の『文学部唯野教授』のパロディを装っている。が、実はこれはパロディではなく、著者の半自伝であり、工学部の実態を世に伝えるセミドキュメンタリーである。また、時として暴露本の様相を呈したりもするのであるが。江藤淳をはじめとした東工大の名だたる文系教授たちがその対象に上げられ、私たち読者は痛快な思いがする。また、大学内外でのヒエラルキーや、文部省(文科省)の無能ぶりと無軌道ぶりもまた全くここに書かれている通りである。それでも工学部教授は⇒2022/09/01
mitei
309
ヒラノ教授を通じて日本の大学の状況、歴史が掴めて面白かった。ヒラノ教授ってすごい人なんだなぁ。2016/12/09
ehirano1
106
理系の大学教官の実態を一部垣間見ることができます。一般人には、まぁそんなもんだわね、という感じかもしれませんが、これからアカデミックポジションを目指す方や既にアカデミアのファカルティポジションの方はかなり興味深く読めるのではないかと思いました。特に後者は、共感する場面がかなり多いのではないかと思いました。2021/04/21
ehirano1
90
「・・・3000枚書くには、その10倍の文章を読まなくてはならない・・・(p55)」。そうですね、これは同感です。書籍等でも参考文献/資料が記載されている場合は、少なくとも記載されている数の倍以上の数を読み込んでいると思います。かの赤川次郎さんは一冊の小説を創るのに100冊以上の本を読むと何処かで読んだ記憶があります。また、龍馬伝を書いた司馬遼太郎はトラック一杯の資料を読み込んだとも記憶しています。本書も、きっとそうなんでしょうね。敬意を払って大切に読まないといけないと思いました。2021/11/20
ehirano1
80
「いいアイデアが浮かんだら、それを頭の中のレジスターにしっかり格納する。1週間程寝かした後、論文になりそうだという感触が得られたら、手が空いている大学院生に・・・(p89)」。アイデアは一旦寝かすというのは外山滋比古氏をはじめ多くの方が言及していますし、作成した文書等も出来上がったらすぐに提出せずに一旦寝かせろとよく聞きます。アイデアが浮かんだからといって、脊髄反射ですぐやっちゃダメよ、当方www。2022/07/03