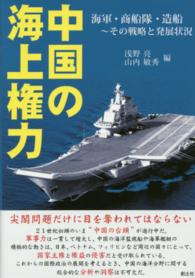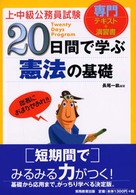- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
二〇一三年春、ついに「リフレ派」が日銀の執行部の中核を占めることになり、量的・質的金融緩和が採用された。これは本当に日本経済の復活をもたらすのだろうか。そもそも日銀は日々何をしている組織なのか。その業務の実態や金融政策の変遷などを、日銀OBで金融政策の第一人者がていねいに分かりやすく解説。アベノミクスで脱デフレに向けて大きく舵を切った日銀は、中長期的に金融システムを安定させていくことが可能なのだろうか―その多難な前途を考察する。
目次
第1章 中央銀行の登場
第2章 主要中央銀行のトラウマ
第3章 日本銀行の登場
第4章 日本銀行の組織と業務
第5章 バブル期までの金融政策
第6章 バブル期以降の金融政策
第7章 デフレ脱却の理論
第8章 クルーグマンと「日本型デフレ」
第9章 中央銀行と財政政策
第10章 「異次元の金融緩和」とアベノミクス
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ito
39
金融政策の専門家による日銀の業務実態や金融政策の変遷を解説した新書である。前半は欧米と日本の中央銀行設立背景が対照的に述べられており、それぞれの制度的立場の違いを認識することで金融政策の違いが理解できる。著者によれば金融政策は電気や水道と同じ社会基盤インフラの一つであり、金融不信によって社会不安を招くと強調する。また本書の特徴はアベノミクスによる大胆な量的・質的緩和への出口戦略を述べているところにある。インフレ目標達成後の中長期的な物価安定と財政の持続可能性との関係が日銀に求められているのである。2013/11/15
izumi
27
日銀の業務についての本だと思って手に取ったが、金融政策に関する広く浅い説明が中心だった(あとがきによると、アベノミクスについて触れる必要が出てきたため、そのような構成になったそう。金融政策の運営が重要な業務だから、間違いではないが)。想像していた内容と違ったが、分かりやすく、知的好奇心が満たされるものだったので、初心者の自分でも読み通すことができた。その時は点でしか見えなかった出来事が、この本では分かりやすく整理されている。今が後にどのように評価されるかが気になるので、この本の更新版が出れば読みたい。2015/10/29
KAZOO
24
日本銀行についてどれほど知っているのか、あるいは日銀のホームページなどにあるがあまりにも大変でという人向きに新書版にして書かれたというのですが、内容は非常にエッセンスが詰まっていて結構歯ごたえがあるのではないでしょうか?リフレ派の人が総裁・副総裁を占めた形になっていますが、あまり変なことはしないと思います。結構世間的体裁を気にされる方々だと思いますので。そのような時期にこの本が出された意義を考えて皆さんに読んでもらいたいですね。2014/06/28
1.3manen
11
財政赤字によるハイパー・インフレーション(HI)という苛酷な経験(046頁~)。日本の場合、消費増税とTPPでスタグフレーションの懸念があると思うのは私だけだろうか? ドイツのHIは4分の1ペニーの価値しかない千マルク紙幣で4千枚包む(049頁)。紙幣が手押し車や乳母車で運搬される。デノミは貨幣額面の変更(053頁)。物価が妥当な感じ、というのは、その人の所得によりけりだろう。金持ちにとってはインフレ感がなくても、貧乏人にとってはインフレなんても財布の懐具合か。ベビーシッター協同組合はいいな(196頁)。2013/09/18
猫丸
10
各国の中央銀行の政策の根底に歴史的トラウマがある、とは分かり易い。日本では昭和恐慌の後は敗戦後のインフレ、列島改造に伴う狂乱物価、そしてバブル崩壊、リーマンショックと大きなインパクトが続いた。ところが現在は派手さはないものの長く続くデフレがじわじわとトラウマ化しており、とにかく緩和を徹底すれば何とかなる論が跋扈する。沈滞した空気を吹き払って景気を好転させれば税収も戻り、デフレも終わるだろうと「考えるフリをする」ところがミソである。貨幣経済においてハイパーインフレの深刻さはデフレなんかとは比較にならぬ。2020/09/21
-
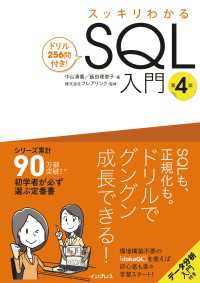
- 電子書籍
- スッキリわかるSQL入門 第4版 ドリ…
-

- 和書
- 着物手帳 〈2015〉