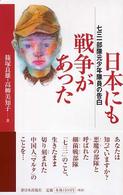内容説明
小説家とは何をするのか?批評家と12人の現代作家による濃厚ライヴ・トークを完全再現。
目次
第1章 前田司郎 出来るだけ稚拙でいたい―『大木家のたのしい旅行 新婚地獄篇』
第2章 長嶋有 「たくらみ」と「私性」―『ねたあとに』
第3章 鹿島田真希 「聖なる愚か者」の社会思想―『ゼロの王国』
第4章 福永信 普通の小説―『アクロバット前夜90°』
第5章 磯崎憲一郎 現実は小説より小さい―『世紀の発見』
第6章 柴崎友香 世界そのものが面白い―『ドリーマーズ』
第7章 戌井昭人 歩けば歩くほどいいものが見つかる―『まずいスープ』
第8章 東浩紀 自分の文学をやることにした―『クォンタム・ファミリーズ』
第9章 円城塔 笑って読み流していただくのが一番なんです―『烏有此譚』『後藤さんのこと』
第10章 桐野夏生 「作家がものを書く」ことについての小説―『ナニカアル』
第11章 阿部和重 真の作家性の在り処とは―『ピストルズ』
第12章 古川日出男 全部小説のためにやっている―『MUSIC』
著者等紹介
佐々木敦[ササキアツシ]
1964年生まれ。批評家。HEADZ主宰。雑誌「エクス・ポ」「ヒアホン」編集発行人。映画・音楽から文学・演劇・ダンス・思想など多彩な領域で批評活動を展開(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ぽち
16
個人的回想「ピストルズ」をがんばって読みきってから向かった安部和重回、そのときの記憶に残っているのは「蓮實重彦はやっぱりすごかった!」というお話だけ笑。で、本書の中ではそれぞれの「絵画」「写真」に対する態度がはっきりとコントラストを成している磯崎回と柴崎回が印象的(しかもこの二人の回は連続している)。お二人は佐々木さんいうところの「保坂スクール」に数えられる作家だと思うけど、とても対照的に感じられた。あと円城回、小説を書くということについて、こちらもいろいろと考えさせられる内容です。2016/10/15
しゅん
14
12人の作家との公開インタビュー。それぞれの作品に対する姿勢の違い、そして語ることに対する姿勢の違いがおもしろい。円城塔の軟体動物のようなふにゃ感にニヤリとしたかと思えば、古川日出男のストレートすぎる言葉の熱量に圧倒される。事前に展開をあえて作り込まないと語る作家が多い中で、阿部和重の細部まで計算を尽くす方法論が目立つ。読みたくなったのは長嶋有や柴崎友香の作品。だけど一番気になったのは、インタビューを受けていない(受けるはずがない)が全体を通してその名前が頻出する舞城王太郎だったりする。2016/12/07
多聞
10
佐々木敦と現代文学を代表する12人の作家たちによる、トーク・セッション集。作家の創作におけるスタイルや、彼らの作品を読む上でのヒントを得ることができ、大変便利な一冊。個人的に長嶋有、福永信、柴崎友香、円城塔、阿部和重、古川日出男の回が良かった。2013/03/21
袖崎いたる
8
方法論の開示を期待して収穫あり。東浩紀と円城塔の2人がおもしろい。「俺の無意識に賭ける!」2018/04/15
OjohmbonX
4
佐々木敦って勝手なイメージだけどマスオさんっぽい。話を聞いてくれるいいお兄さんみたいな。批評家としての対談ではなく、インタビュアーとしてのインタビューに徹する慎ましさ、この退屈さ(褒め言葉)。批評家と小説家の対談で爽快なのは、書き手の意図を超えた豊かな読みを批評家が示して小説家を前進させる瞬間だったとしても、それをインタビュアー佐々木敦に求めるのはお門違いだし、実際ここには無い。それでも12人の比較的若い日本の小説家たちが何を考えて小説を書いているのかをざっと概観できる1冊というのは、案外ないので貴重。2011/09/09
-

- 和書
- 定年世代 新風舎文庫