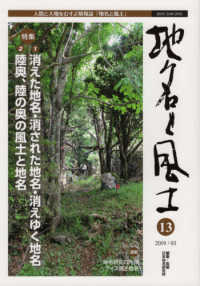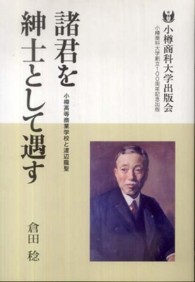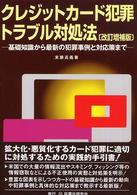内容説明
大河利根川を遡上南限とする鮭。江戸時代から現代まで、その実態を探る。産卵・孵化・飼育と鮭を通しての環境学習。教育現場からの報告。
目次
第1部 利根川の鮭(鮭地蔵;利根川の鮭漁;鬼怒川の鮭魚;増え続ける利根大堰を遡上する鮭;手賀沼の鮭)
第2部 環境学習(鮭を通しての環境学習;鮭の飼育学習)
著者等紹介
佐々木牧雄[ササキマキオ]
1946年生まれ。取手で育ち、法政大学文学部地理学科卒。柏・流山市内の教師を務め退職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
kenitirokikuti
5
図書館にて。2013年刊行。著者は退職した小学校社会科(地理)の教師。銚子を河口とする現在の利根川水系が、鮭の自然遡上限界とされる。かつて、江戸の鮭はこの利根川水系のものだった。鮭は水の匂いを辿って戻るため、水路が新設されて川水の流れが変わると、鮭は迷ってしまう▲塩鮭を作っていたときには、川を上って痩せた方が適していた。養殖の鮭は、脂が乗っている。いま、利根川に鮭はいるのだが、食品価値はゼロのため、漁されず。震災の影響で、鮭の放流が滞っている。多摩川サケの会は、ヤマメに転じている。2019/07/13
-
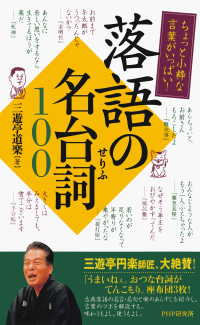
- 電子書籍
- ちょっと小粋な言葉がいっぱい! 落語の…
-

- 和書
- 私の旅日記