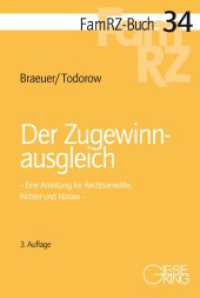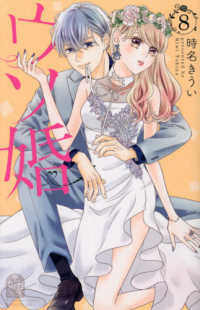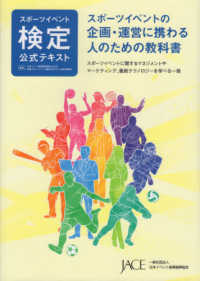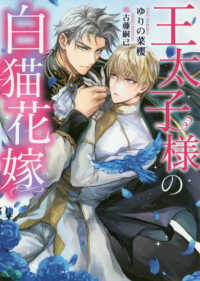出版社内容情報
環境・安全性・プロセス革新・食品の高機能化を実現する21世紀のキーテクノロジー
産学の第一線研究者が食品分野への応用展開と成果を詳述した画期的技術書!!
ドイツUhdeが制作・納入した実プラントの写真を本邦初公開
本書の出版の目的は、21世紀の先端技術として期待されている“超臨界流体技術”が、食品とどのように関わりを持っているのかを広く紹介しようとするものである。
これからの食品産業には、安全で、健康つくりに役立ち、環境に配慮した食品を提供することが強く求められている。また、栄養、嗜好性、生理作用の機能を備えたいわゆる機能性食品の開発も要望されている。 超臨界流体、中でも超臨界二酸化炭素(CO2)は、安全で環境にやさしい流体として食品、飲料あるいは香味成分の分離や加工に広く用いられている。超臨界流体技術実用化の原点は、1970年代末の超臨界CO2による脱カフェインコーヒーとホップエッセンスの製造である。上記2大プロセスは、その後も継続して発展を遂げ、超臨界流体技術の代名詞となっている。
本書が食品に対する超臨界流体の一層の利用を促すよき題材となれば幸いである。
■ 主要構成
第1章 超臨界流体と食品の関わり
第1節 食品産業からみた超臨界流体応用への期待
第2節 CO2を中心とする超臨界流体の特徴
第3節 抽出あるいは反応溶液としての超臨界流体
第4節 超臨界流体抽出プロセス
第2章 有用成分の抽出と食品の高機能化
第1節 食品素材に含まれる高機能成分
第2節 カプシカム色素製造とカプサイシンの抽出
第3節 香料の抽出
第4節 ターメリックの抽出
第5節 シトラスオイルの脱テルペン
第3章 食品製造技術への応用
第1節 シクロデキストリンと超臨界CO2を用いたコレステロールの除去
第2節 魚油中のEPA、DHAの分離
第3節 トリグリセリドの分留
第4節 超臨界膜分離システム
第5節 超臨界流体のエクストルーダへの応用
第4章 酵素反応と殺菌への応用
第1節 エステル交換
第2節 超臨界CO2下における加水分解反応
第3節 酵素・タンパク質の変性
第4節 超臨界二酸化炭素の溶媒特性と酵素反応
第5節 超臨界二酸化炭素による酵素失活
第6節 超臨界二酸化炭素を用いる殺菌
第7節 二酸化炭素加圧殺菌法
第5章 食品の安全性および環境問題への応用
第1節 食品抽出に用いる溶剤と安全基準
第2節 食品への超臨界流体クロマト分析の応用
第3節 土壌評価への超臨界流体の応用
第4節 超臨界水による水産物起源廃棄物の有効利用法
第5節 超臨界水による排水処理
第6節 プラスチックの分解
第6章 超臨界流体の実用化プロセスと装置
第1節 ウーデ高圧技術(株)の超臨界流体技術
第2節 食品分野における超臨界二酸化炭素抽出技術の実用化技術
第3節 超臨界流体の各種装置メーカー
第7章 食品に関する公開特許
■ 内容目次
第1章 超臨界流体と食品の関わり
第1節 食品産業からみた超臨界流体応用への期待<鈴木 功>
1. 食品産業の展開と開発課題
1.1 社会環境の変化
1.2 進歩の過程
1.3 技術開発課題
2. 食品分野における超臨界流体の利用
2.1 生物体からの有用物質の抽出
2.2 抽出溶剤としての超臨界流体二酸化炭素
2.3 機能性食材等の製造
2.4 超臨界二酸化炭素流体による殺菌
3. 食品分野における超臨界流体の応用への期待
第2節 CO2を中心とする超臨界流体の特徴<長浜邦雄>
1. 臨界点
2. CO2の圧力-温度-密度の関係
3. 超臨界流体と常温常圧における気体や液体との比較
4. 超臨界流体+溶質系の相平衡
5. CO2+水系の相平衡とpHの変化
第3節 抽出あるいは反応溶液としての超臨界流体<岩井芳夫>
1. 超臨界流体の定義
2. 超臨界二酸化炭素の物性
3. 超臨界二酸化炭素に対する溶質の溶解度
4. エントレーナ効果
5. 抽出溶剤としての超臨界二酸化炭素
6. 反応溶剤としての超臨界二酸化炭素
7. 超臨界水の物性
8. 反応溶剤としての超臨界水
第4節 超臨界流体抽出プロセス<長浜邦雄>
1. 超臨界流体抽出の原理と特徴
2. 半回分式超臨界流体抽出装置
3. 固体原料からの超臨界流体抽出
4. 抽出プロセスに対する操作因子の影響
5. 食品に関連する超臨界流体抽出の応用例
5.1 超臨界流体による脱カフェイン
5.2 ホップエキスの抽出
5.3 フレーバー類の抽出
第2章 有用成分の抽出と食品の高機能化
第1節 食品素材に含まれる高機能成分<櫻井英敏/宮原晃義>
1. マウス肺発がんに対する食品素材修飾作用
2. ハイオレイックピーナッツ(トリオレイングリセリド)
3. アセロラ(L-アスコルビン酸)
4. 日本ワサビ(6-メチルチオヘキシルイソチオシアネート)
第2節 カプシカム色素製造とカプサイシンの抽出<茂利完治>
1. 超臨界応用製品を製造するに至った経緯
2. カプシカム色素(Capsicum Color)とは
2.1 カプシカム色素の特徴
2.2 カプシカム色素の製造工程
3. カプサイシン
3.1 カプサイシノイドの構成
3.2 超臨界CO2でのカプサイシン抽出方法と特性
3.3 製造プロセスと装置
4. 処理量(原料)および製品紹介
第3節 香料の抽出<石野律子>
1. 食品香料
2. 香味成分抽出分離の従来法と超臨界流体抽出法
3. 天然物の超臨界抽出および分画
3.1 超臨界二酸化炭素中における溶解特性とプロセス選定
3.2 食品香料用香味成分の分離採取の例
第4節 ターメリックの抽出<後藤元信>
1. 精油分の抽出分離
2. クルクミノイドの抽出分離
第5節 シトラスオイルの脱テルペン<後藤元信>
1. 向流接触抽出塔
2. 吸着法
第3章 食品製造技術への応用
第1節 シクロデキストリンと超臨界CO2を用いたコレステロールの除去<長浜邦雄>
1. コレステロールフィーバー
2. シクロデキストリンによるコレステロールの包接化
3. CDによる卵黄中のコレステロールの低減化
4. コレステロール・BCD包接物の超臨界CO2による分離
第2節 魚油中のEPA、DHAの分離<長浜邦雄>
1. EPA、DHAの生理活性
2. 魚油の構成脂肪酸
3. 超臨界CO2によるEPA、DHAの連続精製
4. 硝酸銀水溶液抽出と超臨界CO2抽出の複合化プロセスによるDHAの分離
4.1 硝酸銀水溶液抽出
4.2 銀錯体水溶液の半回分式超臨界流体抽出
4.3 小型充填塔によるEPA+DHA系硝酸銀処理液の連続抽出
4.4 硝酸銀水溶液抽出と超臨界CO2抽出の複合化プロセス
第3節 トリグリセリドの分留<鈴木 功/増田 康>
1. 植物種子からの油脂の分離
2. 動物由来の油脂分離
第4節 超臨界膜分離システム<藤井智幸>
1. 超臨界流体を抽剤として利用するうえでの問題点
2. 超臨界二酸化炭素中での膜分離に関する研究の流れ
3. 超臨界膜分離システム
3.1 実験装置および方法
3.2 Permeability constantおよび阻止率の算出式
3.3 超臨界二酸化炭素中での溶質の膜分離
第5節 超臨界流体のエクストルーダへの応用<鈴木 功>
1. 食品産業とエクストルーダ
1.1 エクストルーダの構造
1.2 エクストルーダ内での物質の変化
1.3 エクストルーダの使用分野
2. 超臨界流体のエクストルーダへの応用
2.1 超臨界流体エクストルージョン
2.2 エクストルージョンプロセスの使用上の制約
2.3 エクストルーダへの超臨界二酸化炭素流体の注入
2.4 設計上の留意点
2.5 プロセス例
2.6 今後の応用分野
第4章 酵素反応と殺菌技術への応用
第1節 エステル交換<生島 豊>
1. 超臨界二酸化炭素の酵素反応溶媒としての特徴
1.1 超臨界二酸化炭素中での酵素の安定性
1.2 基質、生成物の溶解性
2. エステル交換反応
2.1 反応過程および分析
2.2 水分の影響
2.3 温度と圧力の影響
2.4 TG残存率
2.5 エステル交換率
第2節 超臨界CO2下における加水分解反応<長浜邦雄>
1. リパーゼによる加水分解
2. 超臨界二酸化炭素処理による加水分解酵素活性の増加
3. 超臨界二酸化炭素中におけるリパーゼの加水分解反応活性
4. 超臨界二酸化炭素化における加水分解反応の研究例
第3節 酵素・タンパク質の変性-ヘムタンパク質を中心として
<奥 忠武/西尾俊幸/河内 隆>
1. 酵素とタンパク質の変性
2. ヘムタンパク質の機能および構造
2.1 ヘムタンパク質の一次および高次構造
2.2 食品海苔シトクロムの一次および高次構造
3. 超臨界二酸化炭素および加熱処理によるタンパク質の変性
3.1 超臨界二酸化炭素処理による食品タンパク質の調製例
3.2 超臨界二酸化炭素および加熱処理によるヘムタンパク質の変性
第4節 超臨界二酸化炭素の溶媒特性と酵素反応<宮脇長人>
1. 超臨界二酸化炭素の溶媒特性
2. 超臨界二酸化炭素の酵素反応溶媒としての特徴
3. 超臨界CO2における酵素反応と基質溶解度
4. 臨界点付近における特異点挙動
5. 超臨界流体酵素反応の応用
第5節 超臨界二酸化炭素による酵素失活<遠藤泰志>
1. 酵素活性に及ぼす超臨界二酸化炭素の作用
1.1 活性化・非活性化作用
1.2 失活作用
2. 超臨界二酸化炭素による酵素失活機構
2.1 物理的作用
2.2 温度によるタンパク質の熱変性
2.3 pHの低下
2.4 炭酸塩の形成
2.5 相互作用によるタンパク質の立体構造の変化
3. 超臨界二酸化炭素による酵素失活の防止方法
4. 超臨界二酸化炭素による酵素失活技術の応用
第6節 超臨界二酸化炭素を用いる殺菌<下田満哉>
1. 注目したい非加熱殺菌技術
1.1 高圧処理
1.2 パルス電場殺菌法
1.3 その他の方法
2. 超臨界二酸化炭素を用いる殺菌
2.1 ミクロバブルの効果
2.2 連続処理装置の開発
2.3 連続法とバッチ法の比較
2.4 殺菌効果に影響を及ぼす因子
2.5 新たな殺菌理論
2.6 加熱カーボネーション殺菌のシミュレーション
第7節 二酸化炭素加圧殺菌法<熊谷 仁>
1. 研究の背景
1.1 超高圧殺菌と二酸化炭素加圧殺菌の差異
1.2 二酸化炭素加圧殺菌法の発展
2. 死滅速度解析
2.1 死滅速度の解析法
2.2 高水分域における死滅速度
2.3 低水分域における死滅速度
3. CO2加圧殺菌法の殺菌機構
第5章 食品の安全性および環境問題への応用
第1節 食品抽出に用いる溶剤と安全基準<山田 隆>
第2節 食品への超臨界流体クロマト分析への応用<松藤 寛>
1. クロマト分析
1.1 クロマト分析とは
1.2 クロマト分析の分類
1.3 分離と定量
1.4 GCとHPLC
2. 超臨界流体クロマト分析(SFC)
2.1 SFCの長所
2.2 SFCの移動相
2.3 SFCのカラム
2.4 SFCの検出器
3. 食品へのSFCの応用
3.1 SFCの応用
3.2 オフライン分析
3.3 オンライン分析
第3節 土壌構成成分評価への超臨界流体の応用<隅田裕明>
1. 土壌構成成分抽出への超臨界流体抽出の利用
2. 低分子土壌有機成分の抽出
3. 土壌中の金属および土壌有機成分の同時抽出と定量
4. 環境汚染物質の抽出と定量
5. 今後のSFEの土壌構成成分評価のための利用
第4節 超臨界水による水産物起源廃棄物の有効利用法<吉田弘之>
1. 食品廃棄物のの現状と再生利用の特徴
2. 亜臨界水処理による水産廃棄物の高速高度資源化
第5節 超臨界水による排水処理<中森 理/鈴木 明>
1. 超臨界水酸化法の概要
1.1 超臨界水の特性
1.2 超臨界水酸化とは
1.3 反応器の特徴
2. 超臨界水酸化法の適用例
2.1 DXN含有廃液(DXN分析廃液)
2.2 汚泥
2.3 有機塩素系廃液(PCB)
2.4 窒素系廃液(半導体工場廃液)
2.5 含塩廃液(DMSO)
第6節 プラスチックの分解<岡島いづみ/佐古 猛>
1. 超臨界流体について
2. プラスチックのリサイクル
2.1 超臨界流体によるPETのモノマー化
2.2 ナイロン-6の解重合
2.3 ポリカーボネートの分解
2.4 超臨界水によるポリスチレンのモノマー化
2.5 超臨界水によるポリエチレンの油化
2.6 亜臨界水による多層フィルムの分離・回収
第6章 超臨界流体の実用化プロセスと装置
第1節 ウーデ高圧技術(株)の超臨界流体技術<Steinhagen Volkmar(訳:長浜邦雄)>
1. ウーデ高圧技術(株)
2. 超臨界抽出システム
第2節 食品分野における超臨界二酸化炭素抽出技術の実用化動向<福里隆一>
1. 超臨界二酸化炭素抽出技術の工業化状況
2. 超臨界二酸化炭素抽出技術の概要(SFC)
2.1 従来技術としての超臨界二酸化炭素抽出
2.2 最近の超臨界二酸化炭素抽出技術
第3節 超臨界流体の各種装置メーカー
3-1 三菱化工機<南野 康信>
1. 三菱化工機の超臨界二酸化炭素利用技術
2. 超臨界二酸化炭素抽出装置の特長
3. 超臨界利用技術の研究例
4. 納入実績および所有実験装置
5. 実用装置
6. 食品への利用の可能性と留意点
3-2 島津製作所<三宅 正起>
1. ミクロバブルCO2殺菌技術
2. 連続装置の開発
3. MBSS-1000
3.1 製品の特長
3.2 製品の仕様
3-3 東洋高圧<野田 洋二>
1. 超臨界流体反応装置
2. 超臨界流体抽出装置
3. 可視窓付高温高圧セル
3-4 耐圧硝子工業<国分 隆>
1. 耐圧硝子工業の特長
2. 当社の超臨界容器
3. 食品への可能性
第7章 食品に関する公開特許
<長浜 邦雄>
1. 特許の検索および適合特許の抽出
2. 17年にわたる公開特許件数の推移
3. 最近の技術分野別割合の変化
4. 食品関連特許公報に見る技術的展開
■執筆者
鈴木 功
日本大学生物資源科学部 教授
長浜 邦雄
東京都立大学大学院工学研究科 教授
岩井 芳夫
九州大学大学院工学研究院化学工学部門 助教授
櫻井 英敏
日本大学生物資源科学部 教授
宮原 晃義
日本大学生物資源科学部 助教授
茂利 完治
茂利製油(株)松坂臨界工場専務取締役
石野 律子
小川香料(株)舞浜研究所
後藤 元信
熊本大学工学部物質生命化学科 教授
増田 康
(株)エイ・エル・エイ 中央研究所
藤井 智幸
新潟薬科大学応用生命科学部 助教授
生島 豊
独立行政法人産業技術研究所超臨界流体研究センター チーム長
Yan Hao
東京都立大学大学院工学研究科博士課程
奥 忠武
日本大学生物資源科学部 教授
西尾 俊幸
日本大学生物資源科学部 助教授
河内 隆
日本大学生物資源科学部農芸化学科
宮脇長人
東京大学大学院農学生命科学研究科 助教授
遠藤泰志
東北大学大学院農学研究科 助教授
下田満哉
九州大学大学院農学研究院食品バイオ工学講座 助教授
熊谷 仁
共立女子大学家政学部
山田 隆
日本食品添加物協会 顧問
松藤 寛
日本大学生物資源科学部 専任講師
隅田裕明
日本大学生物資源科学部 助教授
吉田弘之
大阪府立大学大学院工学研究科 教授
中森 理
オルガノ(株)SCWO部
鈴木 明
オルガノ(株)SCWO部次長
岡島いづみ
静岡大学大学院理工学研究科博士課程
佐古 猛
静岡大学工学部物質工学科 教授
Steinhagen Volkmar
Uhde Hochdrucktechik GmbH
福里隆一
SCF Techno-Link 代表
南野康信
三菱化工機(株)業務本部研究開発部 研究課長
三宅正起
(株)島津製作所 分析機器事業部事業企画部新事業G マネージャー
野田洋二
(株)東洋高圧 技術部
国分 隆
耐圧硝子工業(株)市場開発企画室