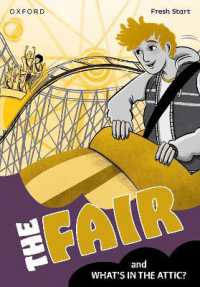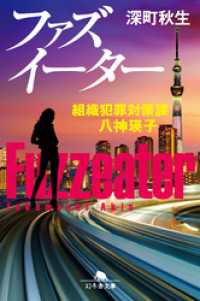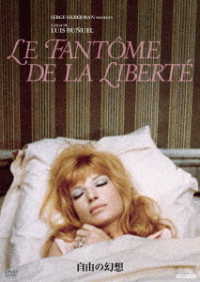出版社内容情報
コストパフォーマンスに優れたFeRAM量産技術・高集積化プロセス・混載技術の最前線とそのノウハウ!
目次
第1篇 強誘電体材料と成膜技術の最前線
第1章 各種成膜技術の最近の展開
第2章 ゾル・ゲル材料と成膜装置
第3章 CVD材料と成膜装置
第4章 スパッタターゲット材料と成膜装置
第2篇 新しい強誘電体薄膜キャパシタ技術
第1章 期待されるキャパシタ特性と作成技術
第2章 薄膜キャパシタの評価とシミュレーション技術
第3章 最近のキャパシタ技術の進展
第4章 微細加工技術
第3編 これからの強誘電体メモリ集積化技術
第1章 ULSI技術からみた強誘電体メモリプロセスの問題点
第2章 各種セル構造と最近の展開
第3章 水素対策技術
第4章 強誘電体メモリの現状と今後の技術課題
内容目次
第1章 先端デバイス動向とウェーハ表面特性への要求
第1章 各種成膜技術の最近の展開【塩嵜忠】
1. 溶液塗布法の最近の展開
2. 新しい塗布溶液
3. 量産用溶液塗布装置の発展
4. CVD法の最近の発展
5. スパッタターゲットと成膜装置の最近の発展
第2章 ゾル・ゲル材料と成膜装置
第1節 塗布液材料【小木勝実】
1. 溶液塗布法とは
1.1 他成膜法と比較した場合の位置付け
1.2 ゾノレ・ゲ〃液とMOD派との違い
2. 量産化に堵ける技術的ポイント
2.1 第1の技術的ポイント
2.2 第2の技術的ポイント
3. 今後の課題
3.1 高集積度化のための表面モフォロジィーのさらなる改良
3.2 結晶化温度の低減化
3.3 耐還元性の向上
4. 薄膜化
5. 感光性塗布液の開発
第2節 連続量産用ゾル・ゲル装置【山田芳久】
1. 開発コンセプト
2. 装置構成
2.1 インデクサ(ID)
2.2 搬送ロボット(TR)
2.3 スピンゴータ(SC)
2.4 薬液キャビネット(CH)
2.5 ぺーク(HP等)
2.6 FFU、安全仕様、その他
3. プロセス
3.1 スピンコート
3.2 べークとスループット
3.3 結晶化アニール
4. 塗布特性
4.1 膜厚均一性
4.2 表面パーティクル
第3節 LSMCD【CarlosA.PazdeAraujo/監訳:宮坂洋一】
1. スタック・セノレのプロセス課題
2. 最新Y-1技術
3. プロセスシーケンス制御
4. 強誘電体FFT
第4節 新しい成膜材料
1. 低温成膜材料【加藤一実】
1. 新規成膜材料(SBT及びSBN薄膜前駆体)の合成
2. SBT薄膜の低温結晶化と強誘電体特性
2.SrBi2Ta2O9薄膜の耐還元性向上【小岩一郎・橋本晃・逢坂哲彌】
1. 強誘電体での問題点
1.1 組成の制御
1.1.1 成膜法の検討
1.1.2 SBT薄膜での組成の影響
1.2 化学状態の制御
2. 結晶化過程の制御
2.1 異相の抑制
2.2 過剰Biの役割
2.3 過剰Bi対策
2.4 ゾル・ゲル法による化学量論値化の検討
第3章 CVD材料と成膜装置
第1節 各社のCVD原料とその特徴
1. 強誘電体用CVD材料【寶地戸道雄】
1. 蒸気圧の測定と開発品
1.1 Sr(dprn)2
1.2 Sr(Ta(OEt)6)2、Sr(Ta(OiPr)6)2
1.3 Ba2Sr(dpm)6+BaSr2(dpm)6
1.4 Bi(OtAm)3
1.5 Ru(EtCp)2
2. 把持昇華型の供給方式
2.1 安定供給
2.2 高純度
2. ICVD原料の高純度化と安全性【高松勇吉】
1. MOCVD用の成膜材料とその特徴
1.1 MOCVD法に用いる原料
1.1.1 MOCVD法-BSTの現状
1.1.2 MOCVD法-PZTの現状
1.1.3 MOCVD法-SBT,Y-1の現状
2. 誘電体薄膜材料の排ガスの除害処理方法
3. 今後の技術課題
3. MOCVD原料とその特性【小林一三】
1. PLZT薄膜作製用MOCVD原料とその特性
2. BST薄膜作製用MOCVD原料とその特性
3. SBT薄膜作製用MOCVD原料とその特性
第2節 強誘電体CVD装置【日高淳一・沢渡義規】
1. MOCVD装置
2. ガス系・有機金属供給系
3. 反応チャンバ
4. 排気・除害系
5. 保安装置
6. 量産用MOCVD装置における今後の課題
第4章 スパッタターゲット材料と成膜装置
第1節 ターゲット材料【長山五月・スーコウコウ】
1. スパッタリングターゲット製造方法の概略
1.1 ターゲットの材料として要求される特性
1.2 ターゲットの製造方法
1.2.1 PZT製造プロセス
1.2.2 SBT製造プロセス
2. セラミックスとしての特性
2.1 ターゲット組成および密度の均一性
2.2 粒径の違い
2.3 X線回折(XRD)
2.4 曲げ強さ試験および熱衝撃試験
2.5 熱伝導率
2.6 PZT昇温脱離ガス質量分析
3. ターゲット密度の違いによるスパッタ特性の変化
4. スパッタにおけるターゲットの問題点
第2節 スパッタ装置【スーコウコウ】
1. FRAM用強誘電体薄膜形成法としてのスパッタリング法
2. PZT系強誘電体スパッタの量産技術の課題
3. 強誘電体量産スパッタ装置と量産スパッタプロセス
3.1 量産スパッタ装置
3.2 PZTの高速スパッタ技術
3.3 PZTスパッタにおける膜組成制御と経時劣化対策
3.4 PZT薄膜の大口径基板における膜厚、組成均一性
3.5 PZTスパッタ薄膜キャパシタの強誘電特性
4. SBT薄膜のスパッタリング
5. 今後の開発課題
第2篇 新しい強誘電体薄膜キャパシタ技術
第1章 期待されるキャパシタ特性と作製技術【宮坂洋一】
1. 高集積化のためのキャパシタ基本特性
2. 強誘電体キャパシタの信頼性に関する技術課題
3. キャパシタ作製技術の課題
第2章 薄膜キャパシタの評価とシミュレーション技術
第1節 基本評価【Joe T.Evans,Jr.・山口泰範】
1. 電気デバイスとしての強誘電体コンデンサ
2. 強誘電体デバイスの成分モデル
3. ヒステリシス・ノレープの分析
4. 信頼性および強誘電体の成分
5. 強誘電体コンデンサのモデル化
6. 残留分極
7. 誘電分極
8. 空間電荷制限電流
第2節 FRAMの品質および信頼性に関わる工業標準の確立【Tom Davenport/訳:井坂順一】
1. FRAM技術開発の始まり
2. FRAM技術の進展に不可欠なインフラストラクチャ
3. FRAM製品の特性および市場の発展
4. FRAMの品質および信頼性
5. FRAMの信術性あるいは品質に関する今後の動向
第3節 シミュレーション技術〔竹尾昌人】
1. 二分極特性モデル
1.1 分極履歴モデル
1.2 分極反転モデル
1.2.1 アブラミ・石橋モデル
1.2.2 MECモデル
2. FeRAMのメモリセル回路の動作解析
第3章 最近のキャパシタ技術の進展
第1節 強誘電性メモリの材料物理学【Ramamoorthy Ramesh・山口泰範】
1. 強誘電体の基礎物理学
2. NVFRAMの動作
3. 初期の開発
4. 薄膜という回答
5. 解決していない物理学上の問題
6. 薄膜技術
7. 商品化について
8. 高誘電率の材料をべースとしたDRAM
9. 強誘電体材料のその他の用途
10. 未来を見つめて
第2節 SBTの進展と1T型への可能性【吾妻正道・有田浩二】
1. SBT系キャパシタ材料の進展
1.1 材料設計技術
1.2 SBT系キャパシタの低電圧特性
2. SBT高集積FeRAM技術
2.1 高集積化への技術課題
2.1.1 強誘電体膜の低温形成
2.1.2 強誘電体膜を薄膜化する成膜技術と低電圧化
2.1.3 耐還元処理
3. 1T型不揮発性メモリヘの可能性
3.1 1T型不揮発性メモリとは
3.2 SBT系材料を用いた1T型不揮発性メモリ
第3節 エピタキシャルBST【川久保 隆・阿部和秀】
1. 二次元圧縮ひずみによるキュリー温度の上昇
2. エピタキシャルBST膜の作製
3. エピタキシャルBST膜の強誘電特性
4. Si基板上のエピタキシャルBSTキャパシタの作製
第4節 MOCVD法による強誘電体Bi4Ti3O12の低温形成【木島 健】
1. 実験方法
2. 結果および考察
2.1 Pt被覆基板上への強誘電体Bi4Ti3O12の薄膜形成技術
2.1.1 Pt上に直接形成したBi4Ti3O12薄膜
2.1.2 TiO2バッファ層効果
2.1.3 ステップ法によるBi4Ti3O12薄膜形成
2.1.4 BiO5バッファ構造を用いたBi4Ti3O12の低温形成
2.1.5 2ステップ法によるBi4Ti3O12の強誘電体キャパシタ形成技術
2.2 Si基板上へのBi4Ti3O12薄膜低温形成
2.2.1 Pt/Bi2SiO5/Si MIS構造とその膜特性
2.2.2 Bi2SiO5をゲート絶縁膜(1層)に用いたMFMIS構造
2.2.3 Pt/Bi4Ti3012/Pt/Bi2SiO5/Si MFMIS構造とそのダイオード特性
第4章 微細加工技術
第1節 強誘電体膜とその電極材料の微細加工用エッチング装置とエッチング技術【大道寺健司】
1. 強誘電体膜とその電極材料の加工性
1.1 材料の種類
1.2 加工の諸問題
2. エッチングヘの要求性能とハードウェアの改善
2.1 不揮発性材料を高遠で精度良くエッチング
2.2 長期間安定なプラズマの発生とエッチング特性
2.3 安定した終点検出機構
2.4 エッチング特性がパターンの粗密に影響されにくいハードウェア
2.5 ウェーハ面内のエッチングの均一性
2.6 誘電率の高い材料をエッチングする場合のマイクロアーキングの発生
2.7 パーティクル発生の低減とウエットクリーニング頻度
2.8 ポスト・トリートメントが可能な機構
3. エッチングプロセスヘの要求
第2節 Ptエッチングプロセス【湯之上 隆】
1. Ptエッチングの課題
1.1 パターン側壁へのデポ
1.2 エッチング装置内壁へのデポ
1.3 石英窓へのデポ
2. Ptエッチングの技術開発
2.1 マスク材料の選択
2.2 マスクの形状の最適化 2.3 プロセスガス条件の最適化
3. サブクオータミクロンPtエッチング技術の展望
3.1 ハードマスクによる高温エッチング
3.2 エッチ後側壁デポ膜を剥離する方法
4. 側壁デポ物形成原理
4.1 実験方法
4.2 実験結果
4.3 側壁デポ形成原理の考察
4.4 側壁デポ低減への指針
第3篇 これからの強誘電体メモリ集積化技術
第1章 ULSI技術からみた強誘電体メモリプロセスの問題点【工藤 淳】
1. メモリセル技術と最近の展開
1.1 メモリセル方式
1.2 メモリセル構造
2. プロセスダメージとその対策技術
2.1 プロセスダメージの実態
2.2 水素劣化と対策技術
2.2.1 強誘電体薄膜の水素耐性向上
2.2.2 電極材料の水素解離作用の低減
2.2.3 絶縁膜中の水素含有量低減
2.2.4 水素ブロッキング
3. FeRAMプロセスの現状と今後の技術課題
3.1 FeRAMプロセス技術の現状
3.1.1 成膜技術
3.1.2 加工技術
3.1.3 電極技術
3.1.4 クロスコンタミネーション
3.2 FeRAM混載技術
3.3 FeRAM高集積化の今後の技術課題
3.3.1 SBT低温成膜技術
3.3.2 耐熱性電極技術
3.3.3 スタック型SBTキャパシタ形成技術
第2章 各種セル構造と最近の展開
第1節 メモリセル方式【國尾武光】
1. メモリセル方式の分類
2. 蓄積容量型メモリセル
3. 1T1Cセルによる動作説明
4. 2T2Cセル
5. 1T2Cセル
6. チェインセル
第2節 メモリセル構造【鳥居和功】
1. メモリセル構造の変遷
1.1 エプレーナーセル
1.2 CUB(Capacitor Under Bit-line)セル
1.3 FCOB(Ferroelectric Capacitor over Bit-line)セル
1.4 プラグ接続を用いた立体セル
2. メモリセノレ微細化の技術課題
2.1 キャパシタ構造
2.2 メモリ部プラグ
第3章 水素対策技術【櫛田-アブデルガファ恵子】
1. 水素による劣化のモデル
2. IrO2上部電極技術
3. キャッピング効果
第4章 強誘電体メモリの現状と今後の技術課題
第1節 ここまできた強誘電体メモリの量産技術
1.強誘電体キャパシタ形成プロセスの現状と課題【中村 孝】
1. 強誘電体成膜プロセス
1.1 ゾル・ゲル法
1.2 スパッタリング法
1.3 MOCVD法
2. 加工プロセス
3. プロセスデグラデーション
4. 信頼性
2.Bi系層状超格子結晶を用いたFeRAMの量産技術【藤井英治】
1. 量産化プロセスの現状
1.1 量産プロセスフロー
1.2 強誘電体キャパシタ形成
1.2.1 強誘電体薄膜形成
1.2.2 強誘電体・電極ドライエッチング
1.2.3 キャパシタ保護膜・コンタクト
1.3 配線・保護膜工程
2. デバイス特性
3. デバイス信頼性
第2節 FRAM混載技術
1.強誘電体メモリ搭載システムLSIの優位性【中村 孝】
1. 強誘電体メモリ搭載システムLSI
2. 強誘電体メモリ混載プロセス技術
2.1 多層配線技術
2.2 セル面積縮小
2.2.1 STCセル
2.2.2 キャパシタ面積縮小
2.3 プロセス温度低減
2. FeRAM混載LSIの実用化を目指して【十代勇治】
1. CMOSとの整合性
1.1 FeRAM混載のプロセスフロー
1.2 FeRAM混載のプロセス課題
1.2.1 CMOS特性への影響
1.2.2 配線形成
1.3 FeRAM混載のプロセス技術
1.3.1 電極へのコンタクト形成
1.3.2 シリコン基板へのコンタクト形成
1.3.3 保護膜形成
2. FeRAM混載のキャパシタに要求される性能と実力
2.1 初期特性
2.2 信頼性
2.3 その他の要求される性能
3. 将来展望-微細化への対応-
3.1 強誘電体低温焼結技術
3.2 電極加工技術
3.3 バリアメタル技術
3.CMOSロジック/FRAM混載技術【山崎辰也】
1. FRAMデバイスの市場動向
2. 富士通FRAMデバイスのプロセス設計方針
3. 富士通0.5μm-FRAMデバイスプロセス技術
4. CMOSロジック/FRAM混載技術
5. 試作チップ
6. PZTのプロセス劣化
第3節 強誘電体メモリ高集積化の現状と今後の技術課題【國尾武光】
1. FeRAMの概要
2. FeRAM混載ロジックLSIの現状
3. 混載対応FeRAMセル面積縮小化技術
執筆者一覧
*所属・肩書き等は発刊当時のものです
■編集委員
塩嵜 忠 奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科教授
宮坂 洋一 日本電気(株)機能材料研究所デバイス材料研究部主任研究員
望月 博 元(株)東芝半導体事業部
崎山 恵三 シャープ(株)IC事業本部プロセス開発センター所長
■執筆者
塩嵜 忠 奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科教授
小木 勝実 三菱マテリアル(株)総合研究所材料技術研究所部長
山田 芳久 大日本スクリーン製造(株)半導体機器事業本部洛西製造部プロセス技術課
Carlos A.Paz deAraujo Chairman,Symetrix Corporasion
加藤 一実 工業技術院名古屋工業技術研究所セラミックス基礎部電子セラミックス研究室主任研究官/東京工業
大学フロンティア創造共同研究センター助教授
小岩 一郎 沖電気工業(株)半導体技術研究所新メモリICPJ主任研究員
橋本 晃 東京応化工業(株)開発本部特定研究一部部長
逢坂 哲彌 早稲田大学理工学部応用化学科教授
寶地戸道雄 (株)高純度化学研究所取締役
高松 勇吉 日本パイオニクス(株)研究所第一研究部部長
小林 一三 日本酸素(株)つくば研究所産業ガス事業本部新材料プロジェクトマネージャー
日高 淳一 日本酸素(株)つくば研究所産業ガス事業本部技術統括部電子機材開発部チーフ
沢渡 義規 日本酸素(株)つくば研究所産業ガス事業本部技術統括部電子機材開発部
長山 五月 UMAT(株)九州工場開発課課長
日本真空技術(株)千葉超材料研究所コロラド研究室(強誘電体メモリプロジェクト)室長
宮坂 洋一 日本電気(株)機能材料研究所デバイス材料研究部主任研究員
JoeTEvans,Jr. President,RADIANTTECHNOLOGIES,Inc.
山口 泰範 ヤーマン(株)先端電子技術第二事業部部長
Tom Davenport VP,Development,RamtronInternational Corp.
井坂 順一 ラムトロン(株)取締役
竹尾 昌人 松下電子工業(株)半導体社プロセス開発センター解析技術部基盤技術開発室技師
R.Ramesh Associate Professor, Department of Phisics University of Maryland
吾妻 正道 松下電子工業(株)半導体社半導体デバイス研究センター機能LSI研究部主席技師
有田 浩二 松下電子工業(株)半導体社半導体デバイス研究センター機能LSI研究部主任技師
川久保 隆 (株)東芝研究開発センターLSI基盤技術ラボラトリー研究主幹
阿部 和秀 (株)東芝研究開発センターLSI基盤技術ラボラトリー研究主務
木島 健 シャープ(株)技術本部エコロジー技術開発センター研究グループ主任
大道寺健司 日本ティーガル(株)代表取締役社長
湯之上 隆 (株)日立製作所デバイス開発センタプロセス開発部技師
工藤 淳 シャープ(株)技術本部エコロジー技術開発センター技師長補
國尾 武光 日本電気(株)シリコンシステム研究所超高集積回路研究部部長
鳥居 和功 (株)日立製作所中央研究所ULSI研究部主任研究員
櫛田-アブデルガファ恵子 (株)日立製作所中央研究所ULSI研究部主任研究員
中村 孝 ローム(株)半導体デバイス研究開発部課長
藤井 英治 松下電子工業(株)半導体社半導体デバイス研究センター機能LSI研究部室長
十代 勇治 松下電子工業(株)半導体社プロセス開発センター開発一部主席技師
山崎 辰也 富士通(株)LSI事業本部ULSI開発部第ニデバイス開発部部長