内容説明
自分でつくる。家族につくってあげる。友だちの顔を思いながらつくる。「いたたぎます」「おいしかった」あたりまえの言葉がうれしい。「台所に立つことは意味がない」と育てられた「親」たちが、子どもの成長を喜び、子どもと台所に立ち始めた。「子どもが作る“弁当の日”」が変えた、すごいこと。
目次
第1章 子どもが作る“弁当の日”の物語(2人のお父さん;仕返し弁当;ピーマンくさっ…;こげこげ弁当;3枚の写真)
第2章 綾上中学校の“弁当の日”(教員生活の終着駅、綾上中学校へ;校長の私も毎回、弁当を作る!;楽しい“弁当見せっこ”は生徒にも伝播)
第3章 ひろがる“弁当の日”(わが子が通う学校で“弁当の日”を実施してほしいのですが;親が「実施してほしい」と訴えても、学校が“弁当の日”をしてくれません;なぜ“弁当の日”実施に校長が反対するのですか;それほど難しいなら、なぜ“弁当の日”は広がっているのですか;多くの困難も予測されながら、“弁当の日”が実施できたのはなぜですか;文部科学省や行政が、一斉に“お弁当の日”を導入してくれたらいいのですが;もし事故が不幸にして発生した場合、責任はだれが、どのようにとるのですか;わが子を小さいうちから台所に立たせるかどうかは、各家庭に任せればいいのではないですか?)
著者等紹介
竹下和男[タケシタカズオ]
1949年、香川県生まれ。香川大学教育学部卒業。県内の小・中学校、教育行政職を経て、2000年より綾南町(現綾川町)立滝宮小学校、2003年より国分寺町(現高松市)立国分寺中学校、2008年より綾川町立綾上中学校校長。2010年3月定年退職。現在はフリーで講演・執筆活動を行っている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
-
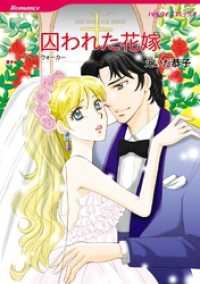
- 電子書籍
- 囚われた花嫁【分冊】 9巻 ハーレクイ…






