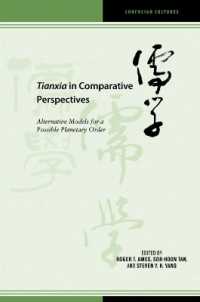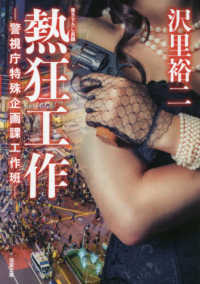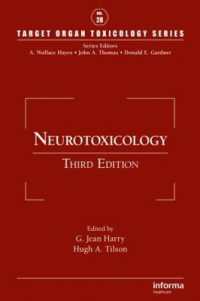内容説明
詩人・小説家・批評家・研究者、松浦寿輝は、どのようにして成ったか。研究と創作のはざまで。
目次
東京大学退官記念講演 波打ち際に生きる―研究と創作のはざまで(作品の効果としての「わたし」;波打ち際という場所;心もとなさ、いとおしさ;三つの特性;スクリーンという波打ち際 ほか)
最終講義 Murdering the Time―時間と近代(「白ウサギ」と「赤の女王」;ダーウィン―物理学的時間の出現;科学と想像の逆説;ミミズの創り出す「時間」;社会進化論からマルクシズムへ ほか)
著者等紹介
松浦寿輝[マツウラヒサキ]
作家・詩人。1954年東京に生まれる。開成中学校・高等学校卒業。東京大学教養学部教養学科フランス分科卒業。同大学院人文科学研究科フランス文学専攻修士課程修了・同博士課程中途退学。パリ第三大学博士(文学)学位取得。東京大学教養学部外国語学科フランス語教室助手。電気通信大学人文社会科学系列専任講師・同助教授。1991年東京大学教養学部外国語学科助教授。1998年同大学院総合文化研究科超域文化科学専攻教授(表象文化論コース)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ソングライン
12
フランス文学の研究者と作家の二つの顔を持つ作者の東京大学退官時の講演「波打ち際に生きる」、最終講義「時間と近代」がまとめられた講演集です。波打ち際とは、不安定さであり、境界であり、異界との出会いの場所であると語り、そこで出会い影響を受けた人々、作品を解説しています。時間と近代では、ダーウィンの種の起源を境に、億単位の時間をめぐる科学的な知が、人間の宗教感を変え、怪物として人間を脅かすようになったと説明し、この時間の束縛からの遁走を夢想するのがこの後の楽しみと締めくくります。2018/08/24
しゅん
12
東大退官講演と最終講義の二本の講義録。それぞれ「波打ち際」と「時間」を主題とした論は、ともに人間が体感出来ない非現実的な「現実」(「波」の向こう側や数千万年という時間単位を人は現実的に感じられない)とどう関係を結んでいくかという問いを抱えており、そのヒントとなる先人たちの試みを一つの流れへと結んでいく言葉は緩やかに移ろいながら読者を新たな場所へと連れてゆく。ヴァレリー、バルト、折口、ヒッチコック、キャロル、ウェルズ、朔太郎。絢爛な名に敬意を表しながら、強固なシステムに組しない揺らぎの感覚が魅力的。2018/04/10
袖崎いたる
3
退官記念講演の書。タイトルの波打ち際ってのは良きトポスよな。自身の千葉県は富津あたりの思い出から語り出してフランス現代思想のお歴々を波打ち際の人として語り懐いてみたり。気になっていたのは最終講義のほう。「Murdering the Time」。不思議の国のアリスにおける3つの時計を検討することが近代の宿痾を剔抉していくことになるという、文学の険しい道のりよ。これが実におもろい。萩原朔太郎は出るわ、ニーチェは出るわ。世俗性と計測可能性と、それから…抑圧性。これが近代化が人間に強いた時間化の実態という次第で。2025/05/19
takao
2
ふむ2023/06/28
保山ひャン
1
東大退官記念講演「波打ち際に生きるー研究と創作のはざまで」と、最終講義「Murdering the Time-時間と近代」、そして、松浦寿輝著作一覧に著者自身がコメントを寄せている。ヴァレリー、バルト、折口信夫、ブルトン、フーコー、ヒッチコック、ゴダール、萩原朔太郎、中江兆民、ダーウィン、ヴェルヌ、ニーチェ、ウェルズ、ボードレール、吉田健一などなど、守備範囲の広さと面白さは格別。最終講義ではとくにルイス・キャロルについて多く語られていて、興味深かった。2015/03/26