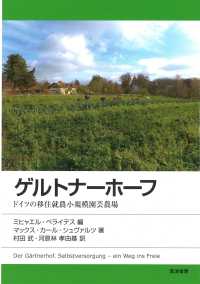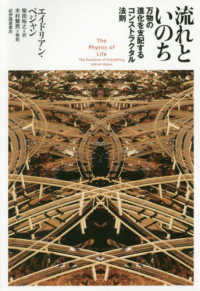内容説明
国が一度やろうと思ったことは、戦争もダムも必ずやると撮り続けた10万枚。カメラばあちゃんの遺した故郷のアルバム。
目次
カメラばあちゃんの誕生
徳山村の四季
石垣りんと徳山村
ダムの足音
映画『ふるさと』
徳山村の人々
徳山村の子供たち
ミナシマイのはじまり
移転地
ミナシマイの前に―増山たづ子と“もうひとつの徳山村”
増山たづ子、昔話を語る
増山たづ子・徳山村年譜
著者等紹介
増山たづ子[マスヤマタズコ]
1917‐2006。岐阜県徳山村(現・揖斐川町)戸入生まれ。1929年、徳山尋常小学校戸入分校卒業後、岐阜の叔父・川口半平のもと和裁修行に励む。1936年、同じ村の増山徳治郎と結婚。一女一男をもうけるが、夫の徳治郎が1945年、ビルマのインパール作戦で行方不明となる。戦後、義父とともに農業の傍ら民宿を営む。1973年、テープレコーダーで村の録音をはじめる。1985年、離村し岐阜市郊外に転居するが、その後も徳山村跡地に通い撮影を続ける
小原真史[コハラマサシ]
愛知県生まれ。IZU PHOTO MUSEUM研究員として「富士幻景―富士にみる日本人の肖像」展などを担当。著書に『富士幻景―近代日本と富士の病』、『時の宙づり―生・写真・死』(共著)ほか。監督作品に『カメラになった男―写真家・中平卓馬』がある。「中平卓馬試論」で第10回重森弘淹写真評論賞を受賞。東京藝術大学・東京工芸大学非常勤講師
野部博子[ノベヒロコ]
岐阜県生まれ。増山たづ子の遺志を継ぐ館代表。滋賀県立大学を退職後、滋賀大学・滋賀県立大学・長浜バイオ大学非常勤講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
けんとまん1007
MAKIO@退職→こどおじニートへ
ぱせり
ほよじー
Koki Miyachi
-
- 洋書
- Little Blue