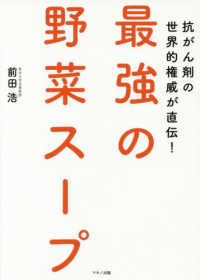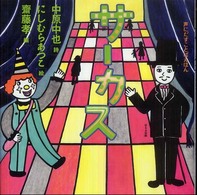内容説明
音楽とはなにか?才能とはなにか?ポップとはなにか?奥田民生、スガシカオ、じゃがたら、フィッシュマンズ、忌野清志郎、桑田佳祐。ひたすら聴く。徹底的に聴く。初めての音楽論、渾身の書き下ろし。
目次
第1部 奥田民生vsスガシカオ(奥田民生;スガシカオ)
第2部 じゃがたらvsフィッシュマンズ(じゃがたら;フィッシュマンズ)
第3部 忌野/清志郎vs桑田佳祐(忌野清志郎;桑田佳祐)
著者等紹介
加藤典洋[カトウノリヒロ]
1948年山形県生まれ。文芸評論家、国会図書館、明治学院大学をへて、早稲田大学国際学術院教授。東京大学文学部仏文科卒。1985年、『アメリカの影』(河出書房新社)でデビュー。以降、現代文学批評、戦後日本論など幅広く評論活動を展開している。著書に『言語表現法講義』(岩波書店、1996年。第十回新潮学芸賞)、『敗戦後論』(講談社、1997年。第九回伊藤整文学賞)、『テクストから遠く離れて』『小説の未来』(講談社、朝日新聞社ともに2004年。第七回桑原武夫学芸賞)などがある(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
marco
38
図書館で借りて読んだ。あまりの素晴らしさに購入を決めた。レスペクト。2015/04/08
しゅん
16
奥田民生とスガシカオ、フィッシュマンズとじゃがたら、忌野清志郎と桑田佳祐。主に3対の音楽家を扱った音楽批評だが、音の印象と歌詞の意味、それとバイオグラフィーでかない重たい場所まで言葉が届いてる。曖昧にしか言えないのだけど、音楽を専門としない、決して音楽の知識も聴取経験も多くない人が、音楽家の精神に共振する文章を残していてビビった。スガシカオの日本/海外の引き裂かれに対して、(村上春樹、そしておそらく自分自身を批判しながら)本当の二項対立は日常/非日常であると喝破するところは、なぜかすごい説得力がある。2021/01/16
ともすけ
9
感想を書こうとしたら下に前のアカウントの感想が。読後感はおおむね前と同じだったので改めて書くまでもないかと。二つ「ともすけ」、それも同じプロフ画像、があるのは少々恥ずかしいことではある。あえて付け加えるならば桑田圭祐の詞の方向性がちょっと前と変わったのかなというのは感じたことは感じた。J-POPも少しずつ変わっているのだなと時の流れを感じる。2016/01/10
peeping hole
4
「町田町蔵は中原中也からだと思う」ほんとそれ。「エレカシは町田康のなりそこない」などなどパンチラインしかない。それにしても潔いタイトル。加藤典洋の本で一番バイブスが高い。フィッシュマンズに三分の一の分量が割かれてるが、それも耳をちゃんとふさいで(聞こえてはいる)ことばと向き合っている。2021/02/17
寺基千里
4
インタビューと歌詞を中心にして、そこに村上春樹や中原中也の詩を交えながらそれぞれのミュージシャンを読み解いていく。文学理論を使い、その歌詞の意図や描かれた背景を分析していたように思う。フィッシュマンズとじゃがたらに関しては情報量が凄まじく、本著を通じてかなりの情報は得られた。 最終的には桑田佳祐の作詞術に落ち着き、彼の歌詞はデタラメなように見えて、実は精巧に作り込まれたものであるという分析は印象に残った。2021/01/04