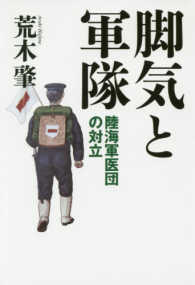内容説明
世の中が大きく変わりゆくなかで、長い間、生活と心のよりどころとなってきた領地のさくらんぼ畑が売りに出された。やがて屋敷を去る日が訪れ、木を切り倒す音が響きはじめる…。百年先の人間の運命に希望をもちながら、目の前にいる頼りない人たちの日々のふるまいを描き出すチェーホフの代表作を、いま新たな翻訳で日本の読者に投げかける。
著者等紹介
チェーホフ,アントン・パーヴロヴィチ[チェーホフ,アントンパーヴロヴィチ][Чехов,А.П]
1860‐1904。ロシア南部のアゾフ海沿岸にあるタガンローグの小売業の家に三男として生まれる。モスクワ大学医学部に通い、その一方でユーモア小説などをつぎつぎと雑誌に発表した。卒業後、すぐれた人間観察力にもとづく中短編の名手として人気作家となっていき、晩年には代表作となった四大戯曲『かもめ』『ワーニャ伯父さん』『三人姉妹』『さくらんぼ畑』を発表してモスクワ芸術座をはじめロシア演劇界に大きな影響を与えた
堀江新二[ホリエシンジ]
大阪大学外国語学部教授。専門はロシア演劇。2001年には第9回湯浅芳子賞(翻訳脚色部門)を受賞
アナーリナ,ニーナ[アナーリナ,ニーナ][Anarina,Nina]
日本演劇研究者。元、ロシア国立演劇大学外国演劇科教授。モスクワ在住(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
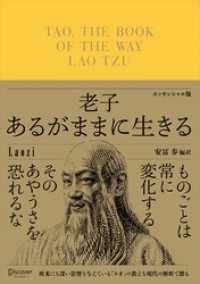
- 電子書籍
- 老子 あるがままに生きる エッセンシャ…
-
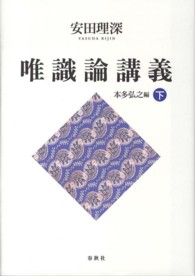
- 和書
- 唯識論講義 〈下〉