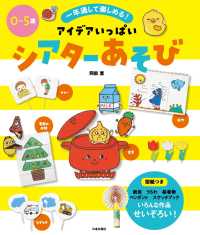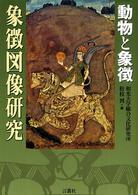内容説明
一九二〇年代、日本では大正デモクラシーのもとで「改造」が流行語となり、「民衆」が歴史の表舞台に躍り出て、それによって逆に知識人のあり方が問われるようになった。そして、民本主義・社会主義など、この時代を席巻した様々な思想は、東アジア各国間で連鎖し合い、それぞれの地域での伝統を踏まえた同名異義の個性的な思想が生み出され、それがまたブーメランのように投げ返されてお互いに影響を与えあったのである。これまで日本発の一方的な伝播だと考えられがちだった二〇世紀初頭の東アジア思想に対する見方を転換し、その位相の違いを描き出す。
目次
1 第一次大戦と東アジア(李大〓(しょう)―中国マルクス主義の父
吉野作造―人格主義とアジア ほか)
2 文学者の問いかけ(森鴎外と夏目漱石―「西洋近代」/「明治国家」との遠近;魯迅と周作人―中国文化の近代転形の象徴 ほか)
3 歴史学と民俗学(柳田国男―平凡・常識の批判的再構築;伊波普猷―帝国の中の近代 ほか)
4 女性と社会(平塚らいてうと与謝野晶子―女性解放をめざして;山川菊栄―マルクス主義フェミニストの先駆 ほか)
5 教育と思想(生活綴方の教師たち―公教育のオルタナティブの開拓;胡適とデューイ―その師弟関係から見える中国近代思想の一齣 ほか)
著者等紹介
趙景達[チョキョンダル]
1954年生まれ、千葉大学文学部教授、専攻、朝鮮近代史
原田敬一[ハラダケイイチ]
1948年生まれ、佛教大学歴史学部教授、専攻、日本近代史
村田雄二郎[ムラタユウジロウ]
1957年生まれ、東京大学大学院総合文化研究科教授、専攻、中国近代思想史
安田常雄[ヤスダツネオ]
1946年生まれ、神奈川大学法学部特任教授、専攻、日本近現代史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。