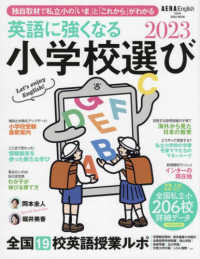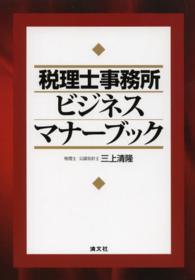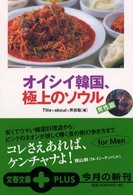- ホーム
- > 和書
- > 医学
- > 臨床医学一般
- > 画像診断・超音波診断学
内容説明
1973年、LauterburがMRIの論文を発表。1982年、本邦初のMRIの臨床応用実施。→そして2010年代。驚異的な発展を遂げ、3T装置が普及期を迎えたMRI。Part1では教育における誤解を正し、Part2では歴史的論文とエピソードを紹介。あまりにも多様化・高度化し、難解になったMRIを解きほぐす一冊。
目次
1 MRIの“予想外?”な真実(イントロダクション;NMRの原理:NMR信号の起源;核スピン系の運動―スピン位相ダイアグラム;核磁化の定常状態とグラディエントエコー法 ほか)
2 MRIはどのように発展してきたか!(イントロダクション;MRIのビッグバン;Mansfieldの業績;MRIの実用手法の確立 ほか)
著者等紹介
巨瀬勝美[コセカツミ]
筑波大学数理物質系教授。1976年東京大学理学部物理学科卒業。81年に東京大学大学院理学系研究科修了、同年東京芝浦電気(株)総合研究所研究員となる。86年に筑波大学物理工学系講師となり、94年筑波大学物理工学系助教授。2001年筑波大学物理工学系教授、2004年から現職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 和書
- ミシェル・フーコー入門