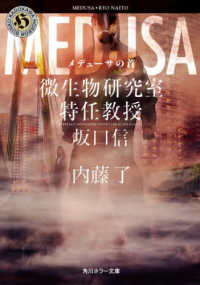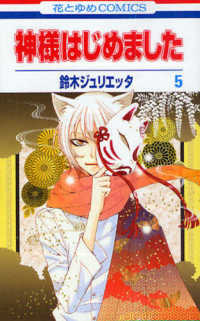- ホーム
- > 和書
- > 芸術
- > 芸術・美術一般
- > 芸術・美術一般その他
内容説明
新自由主義の時代に、世界的に見て最も成功した政策のひとつと評価されるクリエイティブ・ブリテンがもたらした黄金時代の顛末とは。クール・ジャパン、アーツ・カウンシル、オリンピック・パラリンピック、レガシー…。日本は、英国の経験から何を学びとるのか。
目次
序章 「黄金時代」
第1章 ニュー・パブリック・マネジメントのもとで
第2章 クール・ブルタニア
第3章 少数の人ではなく、多くの人に
第4章 アメーバ―その所産
第5章 目標などくそくらえ
第6章 鉛の時代
第7章 オリンピックノ環
第8章 少数のために、多くの大衆のためではなく
終章 ホワッツ・ネクスト?
著者等紹介
ヒューイソン,ロバート[ヒューイソン,ロバート] [Hewison,Robert]
1943年生まれ。英国の文化史家。シンクタンク「デモス」の仲間として文化的コンサルタントも行うなど、現代の文化と文化政策の発展に積極的に関わっている。ランカスター大学、オックスフォード大学、ロンドン市立大学の教授を歴任し、現在はランカスター大学ラスキンセンター名誉教授。ラスキン研究や現代の文化史を中心に著書多数
小林真理[コバヤシマリ]
東京大学大学院人文社会系研究科教授。専門は、文化経営学、文化資源学。文化政策と法、文化行政の制度や方法に関する研究を行う(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
28
2014年初出。本書は、伝統的な意味における文化、芸術と文化遺産(ヘリテージ)に関するものだ。だが、文化の政治経済学も扱う。政治と芸術には、重要な共通点がある。政治と芸術は、どちらも意味をつくり出す手段なのである。生活を形づくる手段でもあるという、社会におけるより広い意味での文化をつくることに、共通の関心を向けている(12頁)。文化政策は、経済政策の一部となった。文化は産業であり、その生産物は商品だった。だが生産手段としては、管理が難しいことが判明した(16頁)。2018/04/15
msykst
17
ロンドン五輪に前後してイギリスの文化政策周りで起こった事柄をルポ的に書いた本。文化論的な話で結論づけようとしているけどそこはなんかとってつけた様な話で、基本的には人事と予算配分の政治的な動きを追う感じ。訳者も書いてるけど、そもそも文化政策の発想は国によってかなり違う上に(英国はアメリカ型と欧州型の折衷らしい)、個々の話は英国のローカルな事情に依るものが多い。にも関わらず翻訳されたのは、東京五輪が近いのもありつつ、日本版アーツカウンシルの導入があったり、日本の文化政策のモデルとして参考になるからかと。2018/02/05
takao
2
ふむ2024/10/19
ノーマン・ノーバディ
0
教訓としては、積極的な文化政策も間違えば関係者の手足を縛ることになりかねないということか。あと当たり前のようだが、多様化が進んで特定の活動と社会的ステータスの結びつきが弱くなった現代では、文化的活動に興味がない人は金や時間があっても参加しない。それだけに教育などで文化に触れる機会を設けておくことが重要になる。文学理論の研究書『マルクス主義と形式』の著者トニー・ベネットが文化社会学に進んだことはうっすら知っていたが、ここで出会うとは。さらに検索したところ博物館研究でも重要な業績を出している模様だ。2025/10/13