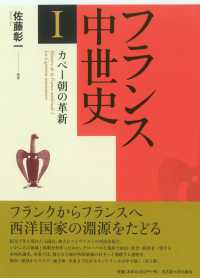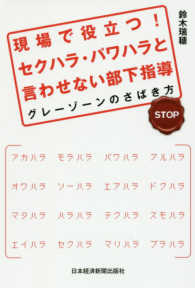内容説明
徳川幕府の下で秘法とされた「土」を用いて脱色するという白砂糖製造の驚くべき方法。国内には伝わらないこの秘法の手掛かりが、当時の交易先ベトナムに残っていた!江戸時代の日本と現代のベトナムを駆け、海を越えた砂糖の源流を記録した貴重なドキュメント!!
目次
第1部 日本の伝統的な砂糖を訪ねて(四国の和三盆;奄美大島の黒砂糖)
第2部 江戸時代の砂糖生産(江戸時代に「輸入」した砂糖と砂糖製造法;日本人が試みた白砂糖製造の秘法;土を使う方法から和三盆の技術へ)
第3部 ベトナムに日本の砂糖の源流を求めて(失われつつあるベトナムの糖蜜;黒砂糖―含蜜糖の色はいろいろ;ベトナムで発見!土を使った白砂糖製造法;グラニュー糖から作る氷砂糖)
著者等紹介
荒尾美代[アラオミヨ]
東京都生まれ。青山学院大学文学部教育学科卒、昭和女子大学大学院生活機構研究科生活機構学専攻、博士課程満期退学。博士(学術)。昭和女子大学国際文化研究所客員研究員。南蛮文化(料理・菓子)研究家(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
くらーく
4
研究報告のような本だなあ。砂糖なんて白いのが当たり前だと思っていたけど、それは遠心分離によって、不純物等を取り除いたからだそうだ。それまでは、どうやって白くしたのかを調査するとのこと。言われてみれば、確かにねえ、と思うけど、どうでも良くない?って気もしないでもない。でも、技術史ってこういうのの積み重ねなんだろうねえ。 着眼点が良いなあ。自分も定年で暇になりそうなので、何か調査してみたいなあ。何が良いかねえ。2021/11/13
木倉兵馬
0
サブタイトルの「土を使って白くする!」に引かれて読んだ一冊。江戸時代、どのようにして製糖業を国内でもできるようにしたのかがテーマの第一部とベトナムでの製糖方法を探る第二部に分かれており、江戸期に行われていた田の底の土を被せて毛細管現象で製糖する覆土法を、近年までベトナムではドン・ムンという砂糖の種類に用いていた、というのが驚きでした。また、今は白砂糖のほうが人気ですが、安土桃山期の日本では黒砂糖のほうが人気で、膨大な利益を得られたそうです。2022/10/18